
「おっ、かかってるかかってる」
シオンは勢いよく釣竿を引いた。
水面近くに魚影が映り、立ち上がって釣竿を立てる。
そうしているうちに、水から飛び出るように魚が見事釣り上げられた。
「うん、なかなかでかいな」
「なんていう魚なんですか?」
アルスが魚を外すシオンの手を見ながら尋ねた。
魚は元気よく体を動かしている。
「これはフナ。食べられるところが少ないんだけどな」
「そうなんですか・・・」
「よっ」
そう言ってから、シオンは外した魚をまた水の中に投げ込んだ。
そして、バケツを持って立ち上がった。
「ま、今日はこれくらいでいいか。帰ろうアルス」
「はーい」
残りの釣具を持ち、アルスもシオンの後に続いた。
コンチェルトに帰ってきてまだ3日しか経っていないが、シオンは暇な時を見つけては趣味の釣りに没頭していた。
アルスを連れて王宮の近くの川に来ていたのだった。
「5匹だから・・・おすそ分けができるかな」
「それは焼くんですか?」
「うーん・・・アルスが料理してくれるか?」
「いいですよ。えっと・・・煮魚にしますね」
「ありがと、じゃ 頼んだぞ」
お互い荷物を持っていない方の手を握って、城へ向かって歩く。
そろそろ城壁が見えてくるか、というところで進行方向から誰かが走ってくるのが見えた。
城で働いている、シオンとアルスも顔見知りの人だった。
「た、大変です!」
その人の必死の形相を見て、シオンとアルスも駆け寄った。
「ど、どうした?」
「今さっき、イリヤ様が城に運び込まれました!」
「運び込まれた?!どうして!?」
「森の中で、大怪我をされているところを発見されまして・・・とにかく、早くお戻りください!」
「わ・・・分かった」
シオンとアルスは大急ぎで城に向かって走り始めた。
城の入り口まで来たところで、門を馬車が潜り抜けていった。
ある程度まで城の庭まで入ると、馬車の扉が開いた。
「姉上、大丈夫ですか」
「ええ。ありがとうね」
イルとイリスだった。
先に馬車から下りたイルが、イリスの手を持った。
その様子を見ていたシオンとアルスは二人に走り寄った。
「イル、イリス様!」
「あ、シオン」
「どうしたんです?たくさん釣れました?」
イルはシオンが持っていたバケツを見ながら尋ねた。
「そ、それよりも・・・聞いてないのか?」
「何を?」
「イリヤさんが、怪我をして倒れてるところを発見されて運び込まれたって」
「ええっ?!」
イルとイリスは同時に声を上げた。
「な、なんで・・・怪我って、大丈夫なの?」
「どの程度の怪我なんですか?!」
「俺もさっき聞いたばっかで・・・急いで帰ってきたんだけど」
「とにかく早く行きましょう!」
イリスはいつもの微笑を消して余裕がなさそうだ。
イルは頷いてイリスの手を引いた。
「アルス、悪いけどこれ運んでおいてくれ」
「は、はい」
シオンは釣具をアルスに手渡した。
そして、イリスの手をとった。
「イル、お前は先に行けよ。俺がイリス様を連れて行く」
「い、いいえ、姉上は私が・・・」
「お前ならイリヤさんを治せるかもしれねえだろ。早く行けっての!」
「分かりました、先に行きます・・・姉上をよろしく頼みますよ」
イルは運動が苦手なりの全速力で、城に向かって走って行った。
「イリス様、急ぎますからどうぞ」
「えっ?」
シオンはしゃがんで背中をイリスに向けた。
イリスは目が見えないので何が起きているのか分からなかった。
「おぶって行きますから。早く」
「だ、大丈夫かしら?」
「イリス様はお軽いですから。平気です、潰れたりしませんから」
「ふふっ・・・じゃあお願いするね」
イリスは少し笑いながらシオンにおぶさった。
背負ってみると、イリスはまるで羽のように軽くてシオンは少しだけ目をぎょっとさせた。
驚いている暇はないのでそのままさっと立ち上がり、振動に気をつけながら城に駆け込んでいった。
「い、イリヤ・・・」
イリヤが運び込まれた部屋に入り、イルは慌ててイリヤが寝かされているベッドに駆け寄った。
周りにはたくさんの人たちが救護にあたっていて慌しい。
イリヤは頭から血を流していて、服が破れているところが多数あった。
破れた服から見える場所にも痛々しい傷がいくつもある。
イルは恐る恐るイリヤの手を触ってみた。
体温はあまりなかったが、冷たくはなくてイルは少しだけ安心した。
その時、シオンとイリスが部屋に入ってきた。
部屋の外でイリスをおろしたため、二人とも歩いている。
「うわ、これは・・・」
イリヤの状態を見て、シオンは思わず口を覆った。
それを聞いたイリスは静かにイリヤの近くまで歩み寄った。
「ねえイル、どんな怪我をしているのか教えてくれる?」
「・・・もう、あちこちから出血してます、切り傷や打撲傷だらけで・・・意識はありません」
「・・・・・・。」
イリスはそれを聞いて、静かにしゃがみ込んだ。
ベッドの端に頭をつけてもたれかかった。
「・・・どうしよう・・・」
そんな様子のイリスを見下ろして、イルはぎゅっと手を握り締めた。
イルには、傷を治すことができる天授力「癒しの願い」を持っている。
それを今使おうとせず、シオンもイリスもそれを使うよう促さないのには訳があった。
5年前。
イルが12歳の時だった。
その頃、コンチェルトでは内戦が起きていた。
原因は、カスタとハープの町のそれぞれの領主の諍いだったが、いつの間にか領土問題にまで発展していた。
国はそれを収めようとしていたが、規模が大きくなっていたためすぐに止めることは困難だった。
カスタとハープに面していたコンチェルトの首都フルートに、毎日のように怪我人が運び込まれていた。
「イル様、どうかこの怪我を治してください・・・!」
イルの前に、肩に剣で斬られて思わず目を逸らしそうになるような怪我をしている人が連れて来られた。
怪我人の周りにいる付き添いの2人が必死にイルに頭を下げた。
「・・・・・・」
イルは無言で立ち上がり、その怪我に両手を近づけた。
ほのかに手が輝き、傷が光で包まれる。
イルが手を離すと、その傷からの出血は止まっていた。
「はい、治りました・・・でも出血がひどいようなので、絶対に安静にしてください」
「あ、ありがとうございます!」
そう言って、お礼を置いて部屋から出て行った。
イルはその後姿を見ながらまた椅子に座った。
そして、疲れた様子で下を向いた。
「・・・はあ」
「どうしたの?」
隣で立っていたイリヤが上から声をかけた。
「・・・もう、戦争は嫌ですね」
「そうだねえ」
「死者や怪我人がどんどん出て・・・本当に、もう嫌です」
両手をぎゅっと握って首を振った。
「今までは、ちょっとした怪我をたまに治す程度だったのに・・・」
「感謝されてるじゃん?」
「・・・知っているくせに、やめてください」
じっ、とイリヤを睨みつけた。
「あー、ごめん」
イリヤは天井を見上げながら目を閉じた。
「私は怪我を治しているんじゃないですよ」
「・・・え?」
「治るなら構わないんです。でも治らないなら・・・」
両手で両腕を抱いて唇をかんだ。
「治せないなら・・・死の宣告をしているだけです」
イルの怪我を癒す特殊な力は、そのままの自然治癒力を高め治療を早めているもののようだった。
要するに、時間が経っても治らない怪我は治すことができない。
本当に稀なことだが、イルが手をかざしても治らない怪我をしている人が運び込まれることがある。
「私が手を置いても、何も起こらなかった時の・・・その人の顔を見るのが・・・」
泣きそうになっているイルを見て、イリヤは部屋の鍵をかけに行った。
そして、えっ、と驚くイルの目の前まで歩いてきた。
「確かにね。他の人にはないものを持っていると、辛くなることもあるよね」
「・・・・・・。」
「でも、イルは人々の苦しみを減らしているんだ。素晴らしいことじゃない?」
「・・・そうですか?」
イルはそっとイリヤを見上げた。
「そうだよ。でもその力を使うかどうかは、イルが決めること。イルの力なんだからね」
「・・・・・・。」
「イルが治したいと思う人にしたらいいよ。イルが人を治すのに疲れちゃったなら、今はお休みにしよう」
そう言いながらイリヤは鍵をかけた扉を見た。
いつ扉がノックされるかと思うと、イルは気が気でなかった。
「・・・でも」
「今日はもうおしまい!イルだって癒されるべきだよ」
「私が?」
「そ。ちょっと外でも散歩しようよ」
「・・・どうせ、すぐに女性の方に行くくせに」
「ははっ、それが女性に対する礼儀ってものでしょ〜」
イリヤはごまかすように笑った。
それを見て、イルも思わずふき出してしまった。
「まったく、イリヤは・・・」
と、笑いながら言いかけて急にイルが止まった。
ゆっくり立ち上がりながら、難しい顔をした。
「・・・本当に、それでいいと思いますか?」
「え?何が?」
「・・・だから、私が・・・その、私が治す人を私が決めていいって・・・」
「当然だよ。自分の力なんだから、使うかどうかも使う時も、全部決めていいんだよ」
「・・・そうですね、分かりました」
そう言ってイルは反対の扉から出て行った。
その後をイリヤもついていき、二人で散歩に出かけた。
イルが部屋から出た後に扉がノックされる音が聞こえたが、イリヤはイルに伝えなかった。
「・・・もし、治らなかったら・・・」
横たわっているイリヤの目の前に立って、イルは手を差し出すのをためらっていた。
「イル、でもやってみないと」
「ええ・・・でも、こんな怪我じゃ・・・」
「・・・やってみないと分からないし、手遅れになったらどうすんだよ」
「・・・・・・」
イルは、くるりと部屋にいる人たちに向き直った。
「・・・すみませんが皆さん・・・部屋から出てくださいませんか」
「え?」
「お願いします・・・」
イルの複雑な心境を察したシオンは、扉を開けて真っ先に無言で外に出て行った。
イリスも立ち上がって、救護班の一人に手を引かれて部屋から出た。
それに皆も続き、部屋の中にはイルとイリヤだけになった。
イルは意を決したように屈んで手を伸ばした。
イリヤに向けて両手を出し、一番出血が激しい頭に手をかざした。
治ってほしいということ以外、何も考えなかった。
しかし。
「・・・ああ、どうしよう・・・」
イルは信じたくなかったが、いつものように自分の手の下で怪我が治ることはなかった。
それを見た瞬間、勝手にイルの目から涙がこぼれた。
「どうしよう・・・」
その時、突然部屋に人が駆け込んできた。
「イル!」
「・・・え?」
振り返ると、そこにはビアンカが息を切らせて立っていた。
手には黄色の大きな水晶のような物が握られている。
「イリヤが、大怪我をしたって聞いて・・・来たんだけど・・・」
イルの近くにビアンカが歩み寄ってきた。
「・・・それは?」
「これは、シードっていう杖だよ。大地の力を秘めた、選ばれた人間にしか扱えない聖玉なんだ」
「聖玉?杖って、どこが・・・」
ビアンカの手にあるシードをまじまじと見つめた。
杖、と言われてもどこからどう見てもただの水晶である。
「それを・・・どうするんですか?」
「うん。イルがこれを持ってみて」
そう言って、その丸い宝石をイルに差し出した。
イルは戸惑いながらもそれを受け取った。
すると、突然その宝石はイルの手の中で光り輝き、形を変え始めた。
光が弱まってから目を開けると、イルの手には黄色い宝石が先端についた杖がおさまっていた。
「・・・やっぱり、癒しの願いを持つイルなら具現化させられたね。よし、急ごう」
「え、え?!何ですか今のは・・・私なら、って・・・?」
「今は一刻を争う。とにかくシードを使って、イリヤをもう一度治そうとしてみて」
「でも、さっき治そうとしたんですが・・・」
「早く」
いつにないビアンカの強めの口調に驚きつつも、イルはシードをイリヤに向けた。
両手の親指でシードを持って横向きにし、手を開いてかざした。
暖かい光がイリヤを包み込んだ。
そしてしばらくすると、イリヤがわずかに身じろいだ。
「・・・うーん・・・」
「あっ・・・」
目を覚ましそうだ、とイルはイリヤに近づいた。
だが怪我は治ったもののイリヤの目は開かれなかった。
「・・・これで、大丈夫なんでしょうか?」
「うん、大丈夫だよ。さすがはイルだね」
「そ、そんな・・・ビアンカ様がくださった、このシードという杖のお陰なのでしょう?」
「私は聖玉を作ることができても、具現化できる人間しか使えない。イルにしかその杖は使えないんだよ」
「・・・??」
わけが分からなくてイルは首をかしげた。
「あの、聖玉って一体何なんですか?」
「属性がついた最高位魔法を使うために必要な聖なる道具。そして、封印に使うための道具」
「封印・・・?何を封印するんです?」
「それは、まだそこまでいってないから分からないんだ。もう少ししたら教えてあげるよ」
「い、いってない・・・??」
聞きたいことすら分からなくなり、イルは思考が止まってしまった。
その時、扉が突然ノックされてそのまま開かれた。
「おい、イル!大丈夫だったのか?ビアンカ様は何をくれたんだ?」
「え、あ・・・」
「イリヤは・・・?」
イリスも心配そうに近づいてきた。
「もう大丈夫です、今は眠っているだけで」
「・・・そう、よかった」
イリヤの横にイリスはまたしゃがみこんだ。
「そうだ、シオン」
「え?」
「忘れてたね。また会ったら、渡す物があるって言ってたのに」
「ああ・・・」
そんなことも言われたっけと、シオンは頭をかいた。
ビアンカは先ほどのシードのような丸い水晶玉をどこからともなく取り出した。
「・・・どっから出したんです?・・・これは?」
「綺麗な宝石でしょ。風の珠、聖玉ファシールだよ。」
「かぜの・・・たま?」
「でもこれはまだ、未完成。シオンがこれを・・・」
ビアンカが話している途中、また部屋の扉がバン、と音を立てて開かれた。
何だろうと全員が振り返ると、そこにはアルスが立っていた。
「アルス、どうしたんだ?」
「た、大変です・・・!」
息を整えるのに必死な様子のアルスに、シオンは近づこうとした。
アルスは必死に言った。
「今さっき、セレナードとバルカローレが・・・戦争を始めたそうです!」
「・・・ええ?!」
―第二章に続く―

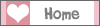
|