
バイエルが両手を上げると、その手の間に光の束が現れた。
そして手を前に振り下ろすと、白い光の矢が飛んで行き泉の淵でアリエスの姿になった。
順番に自分の周りにホロスコープを投げるように配置していき、
12方向にホロスコープたちが置かれると泉全体が輝き出した。
その様子をまるで他人事のように見上げていたフレイだったが、バイエルの視線に気づいてようやく我に返った。
動物の姿のホロスコープや、人間の姿のバルゴ、そしてブラムではなくなったジェミニもこちらを見ていた。
「・・・聖なる水に集いし十二の星達よ、今喜びて此処に力を束ね目覚めよ」
フレイはホロスコープたちに呼びかけるように唱えた。
大地が震え始めてバイエルは思わずしゃがみこんだ。
眩しくて見ていられないほど泉は光を放っており、水面は大きく波打っている。
その泉の上の光の中に向かって、フレイは叫んだ。
「サーペンタリウス、ラエティティア!我は蛇遣い座のオフィウクスなり!!」
ホロスコープたちが螺旋状の光を作りフレイを包み込んだ。
同時に風が巻き起こり、バイエルは腕で顔を覆って衝撃に耐えていたがついに階段から転げ落ちてしまった。
「わあああっ!」
頭を床にぶつけると思ったが、バイエルはふわりとした綿のようなものの上に倒れこんだだけだった。
ショックを和らげたその白く光る物には実体がなく、バイエルから触ろうとすると手をすり抜ける。
驚きに目を瞬かせていると、頭の上から優しい声が降ってきた。
「・・・バイエル、大丈夫?」
見上げると、そこにはフレイがいた。
しかしその身に纏う雰囲気は、いつものフレイのものではなかった。
「・・・フレイ?」
「バイエル、ありがとう・・・あと、もう少しだからここで待ってて」
「ま、まだなにか・・・」
なにかやらなきゃいけないの、と言おうとしてバイエルは口をつぐんだ。
今までのフレイと、瞳の色が違う。ホロスコープたちと同じように、真っ赤だった。
弱くではあるが、フレイの体全体も仄かに光っている。
もう風は吹いていないのに、フレイの髪はふわふわと揺れていた。
人間じゃないみたい。と、フレイを見詰めながらバイエルは率直にそう思った。
「イル、お前はカメか!ナマケモノか?!もっと早く走れねえのかよ?!」
「はあ、はあ・・・ど、どんだけ、走ってると・・・思って・・・・・・げほっ、げほっ!」
「お、おいっ」
イルが咳き込みながら地面に倒れこんでしまい、シオンは慌てて駆け寄った。
羽が生えてシオンの周りを飛んでいる、ファシールも一緒に戻ってきた。
「シオンが先に、行って下さいよ・・・もう、走れませんから・・・」
「ご・・・ゴメンな、突っ走っちゃって・・・でも本当に、急がないと。
それにイルも一緒じゃないとダメなんだって」
「ファシールでも扉は開くんでしょう・・・そんなこと言ったって、
この森の中をどれだけ走り続けたと思ってるんですか・・・」
「カノンの森の中の中心、もうちょっと、もう本当にすぐ近くだと思うから」
「・・・はあー・・・」
両腕に力を入れて大きく息を吐き出し、勢いをつけてイルはまた立ち上がった。
しかし、シオンの視線は地面に向けられたままだった。
「・・・シオン?何見てるんです?」
「んー・・・」
地面にしゃがみこみ、何かを拾い上げた。
シオンの手元を見るため、イルはシオンに歩み寄った。
「・・・石ですか?変わった色ですね」
「こっち側は紫色なのに、こっちは黄色だ。ヘンテコな色だな」
ビー玉ぐらいの大きさの丸い石で、紫と黄色のグラデーションがかかったような色をしている。
シオンはその石を珍しそうに手の上でコロコロと転がした。
「ヘンテコって・・・」
「俺、こういうヘンテコな色のもの好きなんだよ。持って帰りたいなこれ」
「・・・え、好きなんですか?ヘンテコが?」
「へ?うん。普通じゃ面白くないだろ。・・・よし、息は整ったか?」
「あ・・・・・・は、はい・・・」
少し時間が経って、気づけばイルの息切れは収まっていた。
「・・・長距離を移動するときはバイエルのホロスコープに乗せてもらってて楽だったんですけどね・・・」
「そんなことするから体力がさらに落ちるんだろうが・・・おぶってやろうか?」
「・・・大丈夫ですよ、おぶさるなんて情けない・・・」
走ることはできなくても、イルはできる限りの早足で前へ進んだ。
しかしそのとき、少し前を歩いていたシオンが不意に足を止めた。
「・・・・・・。」
遠くに、大勢の人間の気配がする。
木々に阻まれてよく見えないが、話し声や足音も聞こえている。
「・・・あそこなんだな、きっと。テヌートたちがいるんだ」
「ど、どうするんですか?イードプリオルの泉まで行かないといけないのに・・・」
「とりあえず・・・飛んでくか。扉からじゃないと入れないらしいから、扉の前までとにかく行こう。
あいつら全員を相手にしてるヒマはないし」
そう言って、シオンはイルに両手を伸ばした。
一瞬戸惑ったが、抱きかかえて飛ぶつもりなんだと分かるとイルも素直にシオンにしがみついた。
「ちゃんとつかまってろよ。暴れると落ちるぞ。くすぐったりするなよ」
「そんなことするわけないでしょう!・・・でもシオン、大丈夫なんですか?二人で飛ぶと疲れるんでしょう?」
「まあ、これぐらいの距離なら・・・頑張ってみるよ。よし、じゃあ行くぞ」
シオンの背中に白く大きな翼が出現し、それを羽ばたかせて二人は空中に舞い上がった。
「・・・・・・ねえ、サビク」
「ん?どうした?」
「なんか・・・息が、苦しい・・・」
「・・・・・・え?」
イードプリオルの泉の入り口の前にいるテヌートたち。
扉の前でずっと待っていたサビクだったが、突然リムがサビクの服をつかんで訴えてきた。
「・・・リム?どうしたんだよ?熱があるのか?」
「わかんない・・・なんか、体がおかしい・・・」
「え、ええ・・・?」
息苦しそうにそう言うリムに、どうすることもできずにサビクはおろおろと周りを見回した。
そのとき、上空から強い風が吹き付けてきた。
「な・・・なんだ?」
イルを抱きかかえたシオンが、ゆっくりと地上に降り立った。
周りにいるテヌートたちが、驚きの声を上げた。
シオンは着地のタイミングを計ってずっと地面を見つめていて、イルをそっとおろしてからようやく前を見た。
そして、視界に入ったサビクの姿に目を見開いた。
「サビク・・・?こんなとこにいたのか・・・?」
「シオン・・・!」
久しぶりに会えたことに喜び、シオンはサビクに嬉しそうに近づいていった。
歩き出したと同時に、シオンの背にあった白い翼は光の粒になって散って消えていった。
「そ・・・それは俺のセリフだよ。シオン、こんなとこに何しに来たんだ?それに、今の羽は・・・」
「フレイに用があるんだ」
「王子に・・・!?」
驚いて声を上げたが、シオンは気にしない様子でしゃがんだ。
サビクの横にいる、リムに視線を合わせている。
「おーい、久しぶりだな。俺の頭を勢いよく蹴飛ばしてくれたヤツだな・・・リム、だっけ」
リムはシオンと視線は合わせたが、肩で息をしていて何も言わなかった。
そして、サビクの服をつかんだまま苦しそうに目を閉じた。
「シオン、王子に用があるってどういうことだよ」
「ああ、俺はフレイを助けに来たんだ。取り返しのつかないことになる前に、フレイに早く会わないといけない」
「助けに来た・・・?取り返しのつかないことって・・・」
サビクは思わず隣にいるリムの肩を片手でぎゅっと押さえた。
「フレイが大いなる存在を呼び出したら、テヌートは自我を失って誰彼構わず目に付いた人間を殺し始めるんだ」
「・・・・・・。」
シオンの言葉に、辺りに戦慄が走った。
リムも苦しそうにうっすらと目を開けた。
「・・・それ、どういうこと・・・?」
「フレイがホロスコープを束ねた「大いなる存在」つまり「白蛇」の力を操る13番目のホロスコープになったら、
テヌートは人間と、人間が作ったものを破壊する。
人間がいなくなるまで、それが続く。このままだと・・・そんな世界になるんだ」
シオンの言葉に、周りの人間は全く反応ができなかった。
「フレイはこのことを知らない。早く、フレイを止めないと大変なことになる」
「・・・・・・。」
それぞれが驚いて顔を見合わせたが、サビクだけは下を向いたままだった。
痺れを切らしてシオンはサビクの両肩をつかんだ。
「おいサビク、頼むからここを通してくれ!そんな世界にするのがテヌートたちの願いだったのか?違うだろ!?
俺は、フレイのことを助けたいんだ。本当に急がないと手遅れに・・・」
「信じられるかっ!!」
シオンの手を振り払って、サビクは叫んだ。
「・・・サビク・・・」
「どんなことがあっても、誰に何を言われても、絶対に誰もここを通すなって王子に言われた。
王子が出てこられるまで、誰もここは通せない」
「な、なんで・・・なんで信じてくれないんだよ?」
「・・・・・・シオン、俺の兄貴を殺したの、シオンなんだろ?」
「・・・・・・えっ」
サビクは手に持った魔道書を握り締めて、低い声でそう言った。
突然の発言にシオンは戸惑った。
「ど、どういう・・・」
「風の珠ファシールを従える者のみに扱える風の魔法ファシールシンフォニア。
兄貴はその魔法で切り裂かれて死んだんだ。全身ボロボロになって、俺の目の前で・・・・・・」
サビクは強く奥歯をかみ締めた。
そして、有らん限りの力でシオンを睨みつけた。
「シオン、俺はお前の敵なんだよ。
シオンがどんなにすごい魔法を使おうと、どれだけ剣術に優れていようと俺は絶対に負けない。
兄貴を殺した奴に負けないために、俺は今までずっと鍛錬してきた。
兄貴のためにも王子のためにも、ここは通せない」
「・・・そっ・・・」
想像していなかったサビクの言葉に、シオンは言葉を詰まらせた。
悔しさとやるせなさで思わず涙が出そうになったがさらに目を見開いて何とかこらえて声を絞り出す。
「・・・そ・・・うか・・・」
「違うんです!!」
力なくシオンが呟いたとき、シオンの隣でイルが突然叫んだ。
「サビクさん・・・あなたのお姉さん・・・あれ、お兄さん?えっと、とにかくその人は
シオンを殺そうとしたんですよ!それに、シオンがその魔法を放ったのは、弟をその人に・・・」
「イル、いいよ」
話す順序も考えずに慌てて話すイルを、シオンは片手で制した。
「え?だ、だからそのことを話せば・・・あの、その人に弟のアルスを」
「いいから!!」
イルの言葉をシオンは大声で遮った。
驚いたイルは、シオンを見つめたまま動きを止めた。
二人のやり取りを、サビクは何も言わずにずっと見ていた。
「シオン・・・?」
「・・・サビク。本当にごめんな。あの人、サビクのお兄さんだったんだな。お姉さんなのかと思ってたけど・・・。
すごく優しい人だったよな。サビクにもリムにも、いいお兄さんだったんだろうな・・・」
「・・・・・・。」
シオンはゆっくりまたサビクに歩み寄った。
一瞬身じろいだが、シオンが目の前に来てもそのまま動かなかった。
「あの魔法・・・ファシールシンフォニアは、衝動的に放った初めて使った魔法だったんだよ。
でも・・・あの人に対して殺意がなかったかと言われたら、そうじゃない。サビクにとって、俺は敵でいいよ」
シオンは、肩のそばを飛んでいるファシールを手の甲に止まらせた。
そして、もう片方の手で珠の部分をつかんでサビクに差し出した。
「な、なに?」
「これ、サビクに預ける。サビクがこれを持ってれば、リムは苦しくなくなると思う」
「・・・・・・」
手を伸ばすかしばらく迷ったサビクだったが、息を呑んでシオンの手に右手を伸ばした。
ファシールを受け取ると、サビクの手から浮き上がってファシールはサビクの周りを飛び始めた。
「・・・・・・あっ?」
不意に、リムが声を上げた。
その声は今までの苦しそうなものとは違い、いつもの調子になっている。
「急に苦しくなくなった・・・あれぇ?」
「よかったな」
掴んでいたサビクの服をはなして、リムは何度も深呼吸をした。
その様子を見て、シオンは嬉しそうにリムに笑いかけた。
「・・・そっか、やっぱ・・・」
シオンは小さな声でぽつりと呟いた。
その声にサビクが反応するよりも早く、シオンは口を開いた。
「周りのテヌートの中にもリムと同じ症状の人間がいるかもしれない。
でも、サビクがファシールを持ったまま触れたら治ると思う」
「し、シオン、聖玉を渡してしまっていいんですか?」
「ああ、今は聖玉は扉に入るためだけに必要だから、イルのシードがあればいい」
どういうことだろう、と手の中にあるファシールを見てから、サビクとリムは同時に顔を見合わせた。
その二人に、改めてシオンは向き直った。
「俺はお兄さんの仇だから俺の命がほしいだろうけど・・・それ、もう少しだけ待ってくれないか」
「え、いや・・・どういうことだよ・・・?」
「人間とテヌートたちのためにちょっと役立ちたいんだよ。そのあとは、サビクたちの好きにしていいから」
「そ、そんなこと・・・」
「だから、サビク。もう一回だけ言う」
シオンは、真っ直ぐにサビクを見据えた。
「ここを通してくれ。腕ずくで通りたくない。ここにいる誰も傷つけたくない。
だから、どうか俺を信じてここを通してくれ」
「・・・・・・。」
周りの人間はみんな、サビクを見つめた。
リムも、不安そうにサビクを見上げている。
しばらくして、サビクは目を細めて自嘲気味にふふっと笑った。
「・・・敵だなんて言ってごめんな。前に言ったのにな、友達だって。
友達の言うこと、信じられないなんて最低だ」
「サビク・・・」
「いいよ、通って。シオンの言うことを信じる。王子のことを助けに行ってくれ」
「・・・・・・分かった」
サビクは すっと扉の前から移動して本を持っていない方の手を扉に向けた。
「ありがとうな。ファシール、大事にしてくれよ」
「うん・・・大切にする」
「なくしたりしないで、絶対に受け継がせていってくれ」
「わ・・・分かった・・・」
「あ、あとリム」
「・・・なに?」
扉の前に向かって歩きながら、リムに声をかけた。
「お兄ちゃんのことは大切にしろよ。俺の弟は間違っても俺の頭を蹴り飛ばしたりしなかったぞ」
「うー・・・もう蹴らないって約束したもん!大丈夫だよっ!」
「そっかそっか、約束はちゃんと守れよ〜」
手を軽くヒラヒラと振りながらシオンは笑った。
「・・・じゃあイル、シードをここに」
「は、はい」
シオンが指差した扉の真ん中に、イルはシードの先端部分を近づけた。
その様子を見ていたサビクは、イルの手を見て小さく あっ、と声を上げた。
「お前・・・」
「え?私ですか?」
「その、指輪・・・どうしたんだ・・・」
「これ・・・ですか?」
イルの指には、ローチェの指輪が光っていた。
「これは、ある方から頂いたんです。私はお慕いしていたんですけど・・・・・・あ」
ローチェがテヌートだったこと、その他もろもろを思い出してイルは はっとして言葉を詰まらせた。
その様子を見て、サビクは苦笑いした。
「・・・そっか、あの人のいいとこに気づいた人が俺以外にいたんだな・・・ははは」
「え、じゃあもしかしてあなたも・・・」
思わず立ち止まり、サビクともっと話したいと思ったイルだったが、シオンに肩をポン、と叩かれた。
「そういう話もぜーんぶあとにしろ。いくらでもできるから」
「わ・・・分かりました、はい・・・」
「ごめん・・・」
イルとサビクが同時に謝った。
一瞬シオンの頭にはセレナードのマラカ王女の顔がよぎったが、それも何とか首を振って振り払った。
あらためてシードを扉にゆっくりと近づけてトン、と当てた。
すると、扉の淵が白く光ってゆっくりと巨大な扉が開いた。
扉の向こうにシオンとイルが入ると、再び扉は静かに閉まり始めた。
「じゃあなサビク、リム」
「・・・ああ」
「いってらっしゃい・・・」
微笑んで手を振るシオンに、サビクとリムも手を振り返した。
扉が完全に閉まりきるまで、手を振っていた。
周りはまた静かになったが、少しして扉を見つめながらリムが口を開いた。
「・・・サビク、王子に絶対に誰も通さないでって言われたのに通しちゃったね」
「通しちゃったな」
「後悔してない?」
「してねーよ。間違ったことはしてないと思ってる」
「・・・うん」
リムは、サビクの周りを飛んでいるファシールを目で追った。
自分の顔の横に来たときに、人差し指でファシールの宝石の部分を軽くつついてみた。
「ぼくもこれでいいと思う。もうあとは王子たちが出てくるまで、待つしかないね」
「・・・そうだな」
サビクは、これでよかったんだと何度も自分に言い聞かせながら、目の前の高い壁のさらに上にある空を見上げた。
「フレイ、これでぼくはどうしたらいいの?」
「今までと同じだよ。ぼくが力を分けた人は、ホロスコープの力が使えるようになる。
だからバイエルにとっては今までどおり」
「ふーん・・・」
フレイとバイエルは、イードプリオルの泉のそばの大きな石段の一つに座っていた。
バイエルは見とれるようにフレイの横顔を何度も見ていた。
ふわふわと髪がずっと柔らかくなびいていて、赤くて少しだけ光っている目がとても綺麗だと思っていた。
「・・・やっぱり、来ちゃったか」
「え?」
遠くを見ながら、フレイは小さくそう言った。
フレイの視線の先をバイエルも辿った。
「シオン・・・イル・・・」
遠くの階段を下りてくるシオンとイルを見つけて、バイエルは思わず名前を口にした。
フレイは、首を振って苦笑した。
「・・・誰も通さないでって言ったのに・・・サビクなら、通すと思った・・・ぼくのために、通すんだろうって・・・」
立ち上がって、背負っていた剣を鞘ごとベルトから引き抜いた。
フレイが何をしようとしているのか分からなかったが、バイエルもフレイの隣に着地した。
「フレイ、どうするの?ぼく、どうしたらいい?」
「・・・バイエル」
少し悲しそうな表情で、フレイはバイエルの頬に手を伸ばした。
「本当に、ぼくについてきてくれる?シオンとイルと、戦える?」
「うん」
迷う様子もなく、バイエルは素直に頷いた。
その反応に、逆にフレイが驚いた。
「フレイのためなら何だってする。フレイと一緒にいられるなら、どんなことだってするよ」
「・・・・・・ありがとう」
そのまま手を滑らせて、バイエルの頭を柔らかく撫でた。
「じゃあ、行こう。聖地を侵す者には、罰を与えないとね」
フレイが歩き出し、バイエルもその後を追った。
鞘から抜かずにいるランフォルセを、フレイはきつく握り締めていた。
「・・・ようこそ、シオン、イル。星の集う聖地、イードプリオルの泉へ」
「フレイ・・・!」
遠くにフレイの姿を見つけて、シオンはフレイとバイエルに駆け寄った。
「もう、大いなる存在・・・白蛇を呼び出したんだな・・・」
「うん。ぼくは星を束ねる13番目のホロスコープとなり、白蛇の力を手に入れたんだ。ほんとに、長かったよ。
これからここを出て、テヌートたちにもぼくの力を与えに行き、テヌートを最強の人種に作り変える。
手始めに、セレナードと全面戦争だ。この力でぼくは、テヌートの王国を再興して見せるよ」
「・・・・・・。」
シオンは唇をかんだ。
シードを両手で握り、イルは両者のやり取りを見つめている。
「フレイ、俺、母さんに会ってきたんだ。俺の母さんは、ホロスコープをメルディナ大陸に置いた人間の一人だった」
「えっ・・・?」
シオンの言葉に、フレイは驚きの声を上げた。
「白蛇の力がどういう風に語り継がれてきたかは俺も全て分かってるわけじゃない。
でも、白蛇の力はとんでもないものなんだよ」
階段の高いところにいるフレイを見上げながら、シオンは必死に語りかけた。
「母さんが、俺に教えてくれたんだ。大いなる存在、白蛇は・・・」

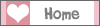
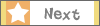
|