
「うわ・・・」
「いたたたっ!!」
突然、何もない空間に出現した二人。
シオンがイルの上に落ちてきた。
「重いですよ、どいてください!!」
「んなこと言ったって・・・よいしょ」
バランスを取り直して、シオンはイルの上から転がるようによけた。
両手で触った床は、まるで水晶でできているかのように透き通っており滑らかだった。
二人の様子を見て、その場所に最初からいた人物がおかしそうに笑っていた。
白くて長い髪の女性で、年齢はシオンとイルよりも少し上程度の外見。
テヌートのようだったが、目の色は赤い。
「ふふ・・・ようこそシオン、イル」
「・・・母さん・・・」
上体を起こして顔をじっと見た後、勢いをつけて立ち上がった。
イルも床に手をついて慌てて立ち上がる。
「シオンの・・・お母様ですか?行方不明だったんじゃ・・・?」
「・・・そうだよ。俺の母さん、クレール・キュラアルティ。父さんが死んだあと俺とアルスを放ってどっか行ったんだ」
「・・・・・・。」
シオンの視線から目をそらし、それでもクレールは二人に歩み寄ってきた。
「・・・もう謝っても仕方ないかもしれないけど・・・本当にごめんなさい、シオン」
「俺はいいよ・・・俺はさ」
床を見つめて、手を握り締めた。
「アルスは・・・1回だけ「母さんに会いたい」って言ったんだよ。でも俺を困らせないためにもう二度と言わなかった。
でも、アルスがどれだけ母さんに会いたいって思ってたか俺はよく知ってる。
・・・あのときだって・・・一目でいいから、母さんに会いたかったって思ってたはずだよ・・・」
あのとき、というのがアルスの最期のときだというのが分かり、イルは思わず目を閉じた。
クレールはシオンに駆け寄って、下を向いていたシオンの頭を抱きしめた。
「ごめんなさい、ごめんなさい・・・本当にごめんなさい・・・!」
「・・・・・・。」
「でもね・・・私、シオンに会えて本当に嬉しいの・・・またこうして話せて本当に嬉しいのよ」
ちゃんと顔を上げればシオンよりクレールの方が背が低かった。
抱きしめられたことに少し照れながら、シオンはクレールの両肩を叩いた。
「あの、母さん・・・それは俺も同じなんだけど・・・」
クレールがシオンから顔を離して、シオンを見上げた。
「・・・母さん、いなくなった日から変わってなくない?いや・・・俺が覚えてる母さんの姿と全く同じなんだけど・・・」
「・・・そうね。それは、ここのせい」
そう言ってクレールは一歩下がって両手のひらを上に向けた。
つまり、この場所全体を指しているようだった。
「ここ・・・そうだ、ここはどこなんだよ・・・?」
「とても綺麗なところですけど・・・」
天井や壁を見回し、シオンとイルは顔を見合わせた。
高い天井も透き通った石や幻想的な色のタイルが敷き詰められていて、壁も床もまるで鏡のようだった。
奥には、大きくて丸い鏡が置いてある。
「あれ、もしかして・・・」
「ジェイドミロワールですか?」
「そうです」
クレールは頷いてジェイドミロワールの近くまで歩いていった。
「私はずっとここからメルディナ大陸を見守っています。それが私の役割なのです」
「役割・・・?なんだそれ・・・」
「光という属性がメルディナ大陸に生まれないために、私がここに存在していることが必要なの。
私はもう何百年もずっとここにいるのよ・・・あのとき以外は、ずっとね」
「・・・あのとき?」
二人が聞き返すと、クレールは床を指差した。
するとその床が透明な椅子になり何もなかった床の上に置かれた。
二人の近くにも同じ椅子が出現し、3人はその椅子に座った。
「もうずっとずっと昔、私には6人の親友と呼べる仲間がいたの。
私たちはとても魔法に長けていたからその研究をして、もっとすごい偉業を成し遂げて見せようとしたわ。
誰にもできなかったことを、私たちならできると信じてずっとね・・・。
でも私たちは仲違いして離れ離れになってしまって・・・
私はこの時が止まったキュラアルティという場所に癒しの司として存在することによって、
他の誰もがメルディナ大陸に来られないようにした・・・。
ルシャンと二人だけでここにいるはずだったのに・・・ルシャンはある日ここを出て行ってしまったの。
彼は普通の人間として生きようとしてある女性と結婚したわ。それがイルの母になった女性。
幸せそうなルシャンを見ていて、私はそれでもいいと思ったのだけど・・・。
程なくしてルシャンは船の事故に遭って・・・私は彼を助けるためにここを出たわ。
ルシャンは記憶をなくしていたけどメヌエットで二人で暮らして、シオンとアルスが生まれて・・・。
けど、彼はラベル家の処刑に携わり・・・そして、この世界からいなくなってしまった。
私はそのとき自分の役割の重大さに気づいて、またここに戻ってきたの。
・・・そう、シオンとアルスを置いてね・・・」
クレールが話している間も語り終えてからも、シオンとイルは瞬きをする以外に何もできなかった。
長い沈黙が続いた後、ようやくシオンが口を開いた。
「・・・母さん・・・何者なんだ・・・?」
「ちょっと、シオン・・・」
やっと言ったのはそれか、とイルは思わずシオンを横目で じとっと見た。
「そうね、この地上では難しいかも・・・分かりやすく言うと、私はメルディナ大陸の人間ではないのよ」
「え・・・」
「私とルシャンは違う世界から来たの。そして、メルディナに存在する私たちと同じ血が流れている者は・・・
私とルシャンの子供であるシオンとアルス。ルシャンと人間の子供であるイルの3人だけ」
「ま、待てよ、それはテヌートってことなのか?テヌートがどっかから地上に来たって?」
「・・・違うの」
クレールは下を向いて静かに首を横に振った。
また訳が分からなくなりシオンとイルは黙った。
「テヌートというのは・・・あとで教えるわ。・・・それで、二人をここに呼んだのは、お願いがあるからなの」
「・・・なんだよ・・・?」
「なんですか・・・?」
立ち上がったクレールは床に出現していた椅子に手をかざしてそれを消滅させた。
そして、二人に向き直った。
「二人に・・・私の代わりに、癒しの司としてここに存在してもらいたいの」
「王子・・・フレイ王子、サビクです」
カノンの町の領主、ハルプトーン家の屋敷の一室。
その広い家の美術室にフレイは一人で立っていた。
扉が叩かれ、フレイは首だけを振り向いてそちらに返事をした。
「どうぞ」
返事だけしてまた前に向き直った。
入っていいのか戸惑ったが、そろりとサビクは部屋に入りフレイの横まで歩いていった。
「・・・綺麗な絵ですね」
「サビクもそう思う?」
フレイは嬉しそうに笑って、一歩下がった。
「この部屋はよく入らせてもらったんだ。この家に来るのは大抵リオーズさま・・・兄上の、用事でね」
「・・・・・・。」
「エリーゼは兄上の婚約者だけど兄上は頻繁には宮殿から出られなくて、ぼくがいつもカノンに来てたんだ。
いわゆる連絡係で・・・でもさ、エリーゼはすっごくいい子だし可愛いし優しいし・・・ははは・・・」
もう100年も前のことで隠す意味もないから言っちゃうけど、本当に大好きだったんだよ。
後半はサビクに囁くように、照れながらそう言った。
「こっちのエリーゼの肖像画は見たことあったけど、こっちはぼくがいなくなってからの絵だね」
「・・・そうみたいですね」
「隣にいるのが、エリーゼの旦那さんになった人か・・・はは、なるほどちょっとクラングに似てるかも」
「・・・・・・。」
無邪気に話すフレイから、サビクは目をそらした。
どうにもフレイの様子に違和感を覚えて話を切り出すことができないでいる。
そんなサビクを察してか、フレイは大きな風景画の前でサビクに振り返った。
「ごめん、それでサビクの用事は何だっけ?」
「あ・・・はい・・・」
ぱっと顔を上げ、後ろで両手を握り締めた。
「その・・・バイエルがさっき、全てのホロスコープを集めたという報告が・・・」
「・・・・・・。」
微笑んでいた表情だったのが、フレイの顔から突然笑みが消えた。
「先ほど、海岸まで行ったらしく・・・その時に、魚のホロスコープ・・・パイシーズを見つけたそうです・・・」
「・・・・・・そっか」
フレイはまた振り返って絵を見上げた。
目はどこか虚ろだった。
「この前、アクエリアを川で見つけて・・・パイシーズが揃えば、12種類か・・・」
「あの・・・王子・・・」
「いよいよだね、サビク」
フレイはサビクに満面の笑みを向けた。
ころころ変わるフレイの表情に、サビクはぎこちなく笑顔を返した。
「これで大いなる存在を生み出し、ぼくがその力を使う。各国が争っている今なら・・・絶対にできる」
「・・・・・・。」
「そして争いをやめない人間たちを一掃し、テヌートだけの平和な世界にする・・・必ず、やってみせるよ」
「お、王子」
「え?」
突然のサビクの声に、フレイはいつもの調子で聞き返していた。
「ど・・・どうしたの?」
「ブラムさん・・・あ、あの・・・ええと、大いなる存在を生み出す言葉、みたいなのは・・・ブラムさんから聞いたんですか・・・?」
「あー・・・ううん、そうじゃないけど・・・あ、でもそうかも」
その言葉の意味が分からず、サビクは目を瞬かせた。
フレイはポケットの中から小さな紙切れを取り出した。
「藍の伝承書を持ってくることはできなかったんだけど、そこの文字部分は書き写しておいたんだ。これにね」
「・・・この文章ですか。王子、読めるんですか?」
「ぼくには読めなかった。兄上なら読めたんだろうけど・・・でもね、ブラムには読めたんだよ」
「・・・なるほど」
紙切れを覗き込んでいたサビクだったが、静かに頷きながらそっとフレイから離れた。
「じゃあ・・・いよいよ明日だね。みんなを集めておいてほしいんだけどいいかな」
「あ、はい・・・俺とリムも行きますね」
「うん・・・」
フレイが突然、サビクの肩に手を置いた。
「え・・・」
「・・・ゴメン。ラスアのことを聞いたとき、ぼく、本当に本当に辛くて、驚いて、悲しくて・・・」
「・・・王子」
「全部・・・ぼくのせいだよ。みんなの犠牲を無駄にしないためにも、絶対にぼく頑張るから・・・だから」
ラスアのことを許してほしい、と言われるんだろうと思ったサビクはそれに対する答えを頭の中で必死に考えた。
しかし、サビクの右肩に力なく手を置いて下を向いているフレイから発せられた言葉は予想と違っていた。
「誰も憎まないで・・・ぼくのことだけを恨んで・・・ぼくのこと、許さなくていいから」
驚愕の余り、サビクは返事をすることすらできなかった。
「バイエル、見せて見せて」
ハルプトーンの屋敷の庭の中。
辺りは薄暗くなっており、夕日が沈みかけている。
「リム?」
「ホロスコープ見つけてきたんでしょ?見せてよ〜」
「いいよ」
フレイがバイエルにつけたテヌートの護衛二人がバイエルから離れた。
バイエルは両手の手のひらを上に向け、ホロスコープを出した。
「・・・・・・これ?」
白い光がパイシーズの形になり、地面に着地した。
それは、ずんぐりむっくりな体型の大きな魚のぬいぐるみだった。
大小2匹の魚が仲よさそうにくっついている。
「うん、パイシーズっていうんだ。泳ぐのが速いんだよ」
「へえ・・・あんまり速そうじゃないなぁ・・・」
「そんなことないもん」
そう言うとバイエルはパイシーズを両手で持ち上げた。
そして庭の外に向かって歩いていってしまった。
どこに行くんだ、とリムは慌ててバイエルを追いかけた。
「ち、ちょっと、バイエル?」
「本当にすごく速いんだよ。この前アクエリアを見つけた大きな川ならパイシーズも泳げるからリムに見せてあげる」
「ええ・・・で、でも、今から?ダメだよぅ、サビクに呼ばれてるし、バイエルも王子から呼ばれて・・・」
「出ておいでカプリコーン、タウルス」
今度は手のひらからカプリコーンとタウルスを出した。
そしてバイエルはパイシーズを抱きかかえたまま颯爽とカプリコーンに乗った。
「リムもタウルスに乗ってよ。そしたら速いよ」
「いや、そういう問題じゃ・・・」
「パイシーズが遅そうって思うんでしょ?ぼく嘘なんてつかないもん」
「だってこんなのが速く泳げるわけないじゃんかぁ・・・」
「だから見せてあげるってば。カプリコーン、走って」
バイエルの声を聞いたカプリコーンは猛烈な勢いで走り出した。
「・・・もう、分かったよぅっ!」
やけっぱちになりリムはバイエルに負けじとタウルスに素早く乗った。
そして、カプリコーンを追いかけタウルスは土煙を上げて全速力で駆け出した。
「すぐ!すぐ帰ってくるから!!待っててー!!」
中庭に残された二人の護衛の青年たちに向かってリムは必死に叫んだ。
カノンの真ん中を流れる大きな川にやってきた二人。
パイシーズの泳ぎの素早さを披露し終わったバイエルは満足そうに川岸に座った。
「ね、すごいでしょ」
「すごいけど・・・すごいけど、水しぶきもすごくてビショビショじゃないっ!」
「だって後ろにいるんだもん」
リムはパイシーズが泳いだときの衝撃で川の水の直撃を受けてずぶ濡れになっていた。
服の端をぎゅっと絞ると水がいくらでも滴ってくる。
「風邪ひいたらどうすんの・・・明日は大切な日なのに・・・」
ビーズで止めてある左右の髪を解いて、リムは首を横に振った。
寒そうなリムを見て、バイエルはパイシーズをしまってアリエスを出した。
「アリエスはもこもこしてるからあったかいよ。ぎゅっとしてたら水吸い取ってくれるよ」
「・・・でもアリエスが寒いんじゃない?」
「へーきへーき、ぬいぐるみだもん」
「ぬいぐるみ・・・」
大きくなっているアリエスに抱きつきながら、リムは呟いた。
「・・・ねえバイエル」
「なに?」
「ブラムさんとはもうしゃべった?」
「うん、たくさんしゃべったよ」
「そっか・・・」
リムは綿のかたまりのようなアリエスの体に顔を埋めた。
もこもこでとても温かかった。
「ブラムさんも・・・ホロスコープなんだよね?」
「うん」
「ブラムさんは、本当はジェミニっていう意思を持たないカラッポのぬいぐるみ・・・なんだよね?」
「そうだよ」
アリエスに顔を埋めたまま、リムは難しい顔した。
「・・・よく分かんないんだ。ブラムさん、普通の人間みたいなんだもん」
「そうだね」
「ジェミニだけはフレイ王子が持ってるんだよね。それ以外のホロスコープは全部バイエルが持ってるの?」
「うん」
「でも、大いなる存在・・・だっけ、それを生み出すにはバイエルが全部のホロスコープを持たないといけないんでしょ。
そのためには王子からバイエルにジェミニを渡さないといけないんだよね?」
「うん」
「そのとき・・・ブラムさんはどうなるの?」
リムの顔はバイエルからは見えなかったが、リムの声が少し震えているのが分かった。
「・・・いなくなるよ」
「・・・・・・。」
その答えにリムは目を見開いた。
しかし、息を呑んだだけで何も言わなかった。
「ブラムさんはジェミニに戻る。そのとき記憶はリセットされる。だから「ブラムさん」って人はいなくなる」
「そ・・・」
そんな、とリムは泣きそうな かすかな声で言ったがバイエルには聞こえなかった。
「ば・・・バイエルは、それでいいの?」
「なんで?」
「ブラムさん、いい人でしょ?バイエルにも優しくしてくれるじゃない!」
「・・・うん」
「そりゃ、ちょっと冷たいって思ったこともあったけど・・・でも・・・ブラムさんが消えちゃっても・・・バイエルは平気なの?」
「・・・・・・。」
体育座りをして膝の上に顔を載せ、木々の奥に夕日があるであろう方向を見つめてバイエルは黙った。
リムは依然アリエスの方に顔を向けたまま。
「フレイがそうしてほしいって言うなら、それでいい」
しばらく静寂が続いたが、バイエルが小さな声でそう言った。
「家で一人ぼっちだったぼくを迎えに来てくれて、家族になってくれたフレイにぼくはお礼がしたいんだ。
フレイが望むことだったら、フレイのためならぼくはどんなことでもしたい。・・・フレイと一緒にいたいから」
そっか、とリムは悲しそうにため息をついた。
アリエスから離れて、そして一人で歩き始めた。
「・・・帰ろう、バイエル。パイシーズ見せてくれてありがとう」
くるりと振り返り、力なくバイエルにそう言った。
しばらくぼんやりとリムの後姿を眺めていたが、アリエスを戻してバイエルもその後を追いかけた。

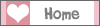
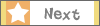
|