
ロイアは自室の部屋を開けて、扉を閉じた。
振り返り視界に入った人物に驚いて少しだけ目を見開いたが、何事もなかったかのように部屋の奥に向かって歩いていった。
「・・・・・・ようこそ、前カペルマイスター殿」
「・・・・・・。」
メヌエットの王宮の警備を抜けなければたどり着けない、城の奥にあるロイアの自室。
その部屋の中で、シオンとロイアは対峙した。
鞘から抜いてこそいないが、シオンはルプランドルの柄を握り締めていた。
しかしその様子にも全く動じることなく、ロイアはシオンに背を向けて本が入っている戸棚を開いた。
「コンチェルトは弱小国のくせに緑豊かでさらに資源は豊富、各国の要人が集う重要な国でもある。
メヌエットの王が侵略目的で大軍をもってコンチェルトを急襲して属国にしようと目論み、その混乱の最中アルスが殺された・・・」
ゆっくりとした口調で話すロイアだったが、シオンは身じろぎしなかった。
ロイアの方を見ようとせずに、じっと床を見つめていた。
「そりゃあ、ここに来るのが妥当だよな。さすがシオン、よくここまで騒ぎも起こさずに来られたな」
「・・・・・・ない」
シオンは絞り出すように言った。
その様子にロイアは少しだけ目を上げた。
「・・・そうじゃない・・・そうじゃないんだろ?違うのにどうしてそんなこと言うんだよ」
「・・・・・・。」
まだ下を向いたままで、泣きそうな声が聞こえてきた。
「ごめんなロイア・・・絶対にそんなはずないのに、疑ってごめん。ほんとごめん」
「・・・おいおい」
シオンはいきなり床にくず折れるように座り込んでしまった。
棚の扉を閉めて、ロイアはあきれたように肩を落とした。
そして、シオンの側まで歩いていった。
「俺が言ったこと聞いてたか?何勝手に否定して謝ってるんだよ。・・・なら、なんでここに来たんだ?」
ロイアの口調はどこかあやすようなものになっていた。
「・・・確かめたかったから・・・でも疑ったからこそ確かめたかったんだよ・・・だから疑ったことを謝りに来たのかも・・・」
「・・・お前な」
シオンの顔をしゃがんで覗き込もうとしたが、髪が邪魔で顔を見ることはできなかった。
仕方なくロイアは上体を起こし、そして腰に手を当てた。
「何が言いたいのか全然分からん。もうちょっと整理してから話せ」
「・・・無理・・・」
「まあ察するに・・・約束、忘れてなかったんだな」
ロイアがそう言うと、シオンは突然顔を上げた。
「うん・・・忘れてない」
立ち上がり、ロイアの右目を見つめた。
「ロイアの片目が見えなくなったのは俺のせいだ。それなのにロイアは俺のことかばってくれた・・・」
「シオンのせいじゃないし、怪我したのは自分のせいだと周りに言ったのは俺の気まぐれ。
それでもシオンが責任を感じるって言うなら・・・俺はなんて言った?」
「・・・・・・。」
いざロイアに見つめ返されると、シオンは思わず目をそらしてしまった。
「・・・俺の剣士として支えてほしい・・・俺は絶対シオンを裏切らないから、シオンも裏切るな・・・だよな」
「そう。実際にシオンは頑張ってくれただろ」
「でも、俺はもうこの国のカペルマイスターじゃない。裏切ったようなものだろ・・・」
「いいんだ、今はもうレインがいる。・・・・・・それで」
何かを思いついたように、ロイアが視線を動かした。
今までと声の調子が変わった。
「シオン、できればでいいんだが・・・・・・あ」
「え?」
ロイアがシオンの後ろを見て動きが止まった。
シオンが振り返ってみると、扉が少しだけ開いていた。
「そろそろ入ってもいい?二人とも」
扉から顔を半分だけ覗かせていたのは、ビアンカだった。
ロイアは何も言わず、目を大きく見開いたままただ非常にゆっくり頭を縦に振った。
「いやー、本当に久々だねロイア。病気だとか怪我だとかいう噂も聞かなかったし、健康的に過ごしてたかな」
「・・・・・・。」
「・・・・・・。」
ロイアの部屋に入りながらビアンカだけは嬉しそうに懐かしそうに話しているが、ロイアは一切声を発していない。
また、そんなロイアの様子を見てシオンも発言できていなかった。
「シオン、ロイアとの話はもう終わった?途中だったらゴメンね。こっちの廊下に誰か来そうだったから」
「は・・・いえ・・・」
「話して分かったと思うけど、これがもう一つのテヌートたちが仕掛けたことだね。メヌエットの兵に扮して、
コンチェルトの王宮を襲撃する。コンチェルトからの報復やそれに対するメヌエットの対応がまた戦争の火種になる。
でも当事者たちはとっくに引き上げていて、後は野となれ山となれって」
そう言いつつビアンカはシオンに紫苑の伝承書を差し出した。
驚いたシオンはその本を受け取るための手を出せなかった。
「え、あの、ビアンカ様・・・?」
「私が読んで分かったことは全部シオンとイルに伝えた。残りの2ページを探してその本を完成させて。私はもう・・・」
「・・・あ、兄上・・・」
「・・・ん?」
二人の会話は全く耳に入れていなかったロイアが、ついに口を開いた。
意を決して発言したせいか、声が少し裏返っていた。
「・・・なに?」
「ロイア様!ロイア様、おられますか!!」
ビアンカが首を傾げて尋ねたのとほぼ同時に、扉が激しく叩かれた。
「な・・・なんだ・・・?」
それどころではなかったがとりあえずロイアは扉に向かって歩いていった。
その途中で、また外から声がした。
「侵入者です!いつの間にか城内に入り込んでいて・・・」
「・・・名前は何と言っていた?」
「はっ、イルと名乗っているようです」
「・・・・・・。」
部屋の中にいた3人は思わず黙った。
ロイアは説明を求めてシオンに振り返った。
「いや・・・3人で分かれて城に入ったんだけど・・・イルだけ見つかっちゃったみたい・・・」
「私が一緒に行ってあげればよかったかな・・・?」
「・・・・・・はあ」
ロイアは大きなため息をついてから扉を開けた。
「そいつは俺の客人だ、放してやれ。ほらシオン、迎えに行って来い」
「お、俺が・・・?」
「お前なら城内の人間と面識ある奴もいるだろ。とっとと回収して来いよ」
「回収って・・・」
しぶしぶシオンは部屋の外に出て行った。
扉が閉まるとシオンを見た兵士の驚いた声が聞こえたが、ロイアは気にせずまたビアンカと向かい合わせの椅子までやってきた。
「兄上・・・」
「ほんと、こうやって向かい合って話すのも何年振りだろうね。いつもいつも私はロイアに怒られてばかりで」
ビアンカは ふふっと苦笑しながらゆるく首を横に振った。
「私が勉強を抜け出して散歩に出ても連れ戻しに来るし、隠れても探し出してくれたし・・・。
どっちが兄か分かったもんじゃないよね。ロイアは本当にすごいよ。これからも頑張って」
「違います」
ビアンカの言葉を遮って、ロイアは机を両手で叩いた。
微笑んでいたビアンカの表情が少しだけ変わった。
「俺は何もできないんです。今回の・・・今回のコンチェルトの侵略騒動で本当に分かりました。俺じゃダメなんです」
両手を机の上で強く握り締めているその手は、力を込める余り震えている。
「兄上を追放した俺が言うなんて間違ってることはよく分かってます。自分でやっておきながらこんなことを言うなんて、
自分で自分に、吐き気がするほど最低だって感じてます。本当によく分かってるんです・・・でも・・・」
ロイアは勢いよく立ち上がり、そして静かに頭を下げた。
「・・・兄上、どうかメヌエットにお戻りください。この国にはあなたが必要です。この国を治めるのはあなたしかいないんです」
「・・・・・・。」
「申し訳ありませんでした。お願いします、兄上・・・」
頭を下げたまま動かないロイアを見て、ビアンカは立ち上がった。
そして、そっとロイアの頭に手を置いた。
下を向いたままロイアは目を大きく見開いた。
「ありがとう、ロイア。私のことを必要だって言ってくれるなんて、本当に嬉しいよ」
ビアンカはテーブルをよけてロイアの前まで行き、しっかりとロイアの両肩を持った。
ゆっくりとロイアが顔を上げた。
「ずっと分かってたよ。ロイアは自分が王位を継ぎたいわけじゃなかったって。
私にちゃんとするようにいつも怒ってくれていたのは、そのためだったんだよね」
「・・・・・・。」
ロイアは不安そうな顔をして目をそらした。
「それは・・・兄上の力で、俺の・・・心を読んだから分かったことですか?」
「え?あはは、やっぱり私の天授力のこと、ロイアは分かってたんだ」
ロイアの肩から手を離して、ビアンカは明るく笑った。
しかしロイアは慌てて首を横に振った。
「ち、違います、どういう力かは知りません。でもきっとそういう力があるんだろうって・・・」
「私の天授力は触ったものの過去を見る力だよ。けど、ロイアの過去を見たことは一度もない」
「え・・・」
ビアンカは両手を後ろで組んで、一歩後ろに下がった。
「ロイアの過去なんて見なくても、私はずっとロイアのことを見てきたよ。ロイアが生まれたときから見てたんだから。
ロイアがいつも私のためを思ってくれていたことも、ずっと分かってたよ・・・ロイアの期待に添えなくて、ごめんね」
そのままどんどん後ろに下がって行き、扉の前で立ち止まった。
「この国に必要なのはロイアだよ。私じゃない。メヌエットを治められるのはロイアだけだよ。
私は行かなければいけない場所があり、やらなければいけないことがあるんだ」
「そんな・・・」
「大丈夫、ロイアなら絶対に大丈夫。私がどこにいてもロイアの活躍が聞こえてくるぐらいの王様になれるよ」
ロイアは思わずビアンカを追って足を踏み出した。
それを見てビアンカは手を差し出して、ロイアの右手をぎゅっと両手で握り締めた。
「兄上・・・メヌエットには・・・いや、俺には兄上が・・・」
「・・・私がどこにいてもロイアの幸せを願ってるよ。最後まで頼りない兄でごめんね・・・さようなら」
手をぱっと離して、そのまま扉を開けて素早く走り去ってしまった。
ビアンカに握られていた手を宙に浮かせたまま、ロイアは泣きそうな顔でその場で立ち尽くした。
「・・・・・・分かりました。俺のことを許してくださって、ありがとうございます」
半分開いた扉を見つめ、呟くようでもなくはっきりと伝えるようにそう言った。
「おーい、ご気分はいかがですか」
「シオン!?何してるんですか、早くここから出してくださいよ!」
「・・・ほんと情けねえなあ・・・」
「なんですって?!」
牢屋越しに噛み付かんばかりの勢いでイルは言い返した。
私を一人置いていくからでしょう、とか、周りのことも気にかけられないんですか、とか、
必死に横で訴えを並べ立てているイルを尻目にシオンは牢番に話をつけていた。
錠前が開く高い音が響いて、ようやくイルは状況を察して鉄格子を押して外に出てきた。
「出られてよかったな」
「まったく・・・ビアンカ様もいつの間にかいなくなっちゃうし、私一人で隠れながら進めるわけないでしょうが・・・」
「はいはい、イルはずーっと見張ってなきゃ何もできないんだな。ちゃんとついててやるから歩くぐらいはしろよ」
「なんて言い草ですかっ!本当に大変だったんですからね!?」
「へいへーい」
ほとんど相手にしていない様子で、シオンは階段を上っていった。
まだメヌエットの王宮内にいるシオンとイルだったが、数分するとようやくイルの怒りも収まってきた。
「・・・で、ロイア様には会えたんですか?」
「会えたし話もしたよ。ついでに途中でビアンカ様も入ってきて、ようやく話の概要がつかめてきた」
「ビアンカ様まで・・・あ、話の概要って?」
シオンはビアンカからもらった紫苑の伝承書を取り出した。
「・・・それ、紫苑の伝承書?」
「ビアンカ様からもらった。破れた2枚のページを探してほしいってさ」
「そんな・・・途方もない話ですね・・・」
「・・・ほんとにな」
破れたページがある場所まで本を開いて何気なくシオンはページに目を落とした。
しかしやはり文字を読むことはできない。
「とりあえず、話して分かったことはメヌエット軍のコンチェルト襲撃もテヌートたちが仕組んだことだったってこと。
・・・これでコンチェルトから報復でもしようものなら本格的な戦争になってたな」
「・・・シオンがロイア様を斬りつけでもしてたら本当にそうなってたでしょうね」
「・・・・・・。」
複雑な表情を浮かべて、シオンはパタンと紫苑の伝承書を閉じた。
「じゃあ・・・これからどうするんですか」
「当然だろ。フレイを止めにいく」
「・・・え」
本を脇に抱えて、城の広間の出口に向かって歩き出した。
「バイエルがホロスコープを全てそろえる前に、フレイに会って話す」
「話すって、何を・・・?」
「テヌート以外の人間を消滅させてまでモデラートを再興するなんて間違ってる。絶対にフレイなら話せば分かるはずだ」
「それは・・・フレイなら、きっと分かってくれると思いますけど・・・」
「フレイが一人でそんなこと背負ってるなんて可哀想すぎる。早くセレナードに・・・・・・あ?」
「・・・・・・え?」
突然歩みを止めて、シオンが片手を頭に当てた。
イルも違和感を感じて立ち止まって辺りを見回した。
「だ・・・誰だよ?」
二人の頭の中に、誰かの声が響いた。
シオンにはとても聞き覚えのある声だった。
「・・・シオン、聞こえていますか?」
それは、優しい女性の声だった。
シオンの脳裏に、一気に幼い頃の記憶がよみがえった。
「か・・・母さん?」
「えっ・・・これ、シオンのお母様の声なんですか・・・?!」
城の中にいる人たちが騒いでいる二人を不思議そうに見ていくが、二人はそれどころではなかった。
「母さん、どこにいるんだよ?!どこから話してるんだ!?」
「・・・私はそこから遠く離れた場所にいます。二人に伝えたいことがあるのです・・・」
「つ、伝えたいこと・・・?遠く離れた場所って・・・」
そう言った瞬間、突然二人の体が薄緑色に輝き出した。
「わっ!?」
「な・・・なんですか・・・?」
「私がいる場所に・・・来てくれませんか?お願いです・・・」
自分たちの状況に驚いたシオンだったが、頭に響く声音に仕方なさそうに頷いた。
「・・・分かったよ、何でもしろよ・・・」
「ち、ちょっと、シオン?」
「イル、ごめんな。いいぜ母さん、行くから」
「・・・ありがとう」
嬉しそうな声が聞こえたかと思うと、室内だというのに強い風が吹き始めた。
風が渦を巻いて二人を包み、光が収まった頃には王宮内から二人の姿は消えてしまっていた。
周りに残された人たちは、目の前で起きたことが現実だと信じられない様子でしばらく動くこともできなかった。
「・・・・・・行っちゃった」
驚いていないのは、遠くの柱の陰からその様子を見ていたビアンカだけだった。

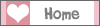
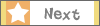
|