
「・・・・・・え?」
シオンは顔を上げたが、イルも上を向いていて空を見つめていたので視線が合うことはなかった。
「・・・私の父の名前、知ってます?」
「え・・・し、知らない・・・」
「イリヤと姉上の父が亡くなって、すぐに母は再婚しました。その人は、テヌートだったそうです」
「テヌート・・・?」
急なイルの話に泣くことを忘れて、シオンは片手で頬の涙をぬぐった。
「でも、私が生まれる前に父は船舶事故で亡くなりました。母も一緒だったのですが、母は奇跡的に助かりました。」
「・・・・・・。」
「そして私が生まれて・・・母が亡くなって、姉上が予言の力を授かり、私たちは3人でコンチェルトの王宮に招かれました」
「・・・は、はあ・・・」
掴んでいたイルの服を離して、シオンは少し身を起こした。
「私は父の顔を見たことはありません。ですが、名前は「ルシャン」といったそうです。」
「え・・・・・・!?」
シオンは驚きのあまり息を呑んだ。
「俺の・・・父さんと、同じ名前・・・?」
「・・・これ、偶然ですか?」
「俺の父さんは・・・」
一度言葉を詰まらせたが、シオンは手を握り締めて話し始めた。
「メヌエットの王宮で働いてた母さんが、浜辺に意識不明で流れ着いていた父さんを見つけたって言ってた・・・
記憶がなかったけど、名前が剣に刻まれてたんだって・・・結婚して、母さんの苗字の「キュラアルティ」を名乗ったって・・・」
それを聞いて、イルは思わず笑ってしまった。
「なっ・・・どこがおかしかったんだよ!?」
「いいえ・・・近くにいたのにお互い両親の話すら一度もしなかったんですね・・・話せばすぐに分かったのに・・・」
「じゃ、じゃあ・・・もしかして・・・」
イルは何も言わずに、シオンの目を見て頷いた。
体の力が抜けたシオンもイルの目を見つめて ほーっと息を吐き出した。
「・・・俺、メヌエットに行ってくる」
「え?」
しばらくしてまた前に向き直ったシオンは、目を擦りながらそう言った。
「そんな・・・単独で・・・?」
「メヌエットが何のためにこんなことをしたのか、ロイアが何考えてんのか聞いてくる」
「む、無理ですよロイア様にこの状況で会うだなんて・・・王の動向を尋ねてからでないと・・・」
「・・・アルスが殺された、そのことは絶対に許せない。でもコンチェルトがメヌエットに宣戦布告する前に、
俺が直接ロイアに話を聞く。ただの侵略なら・・・そのときは・・・」
「・・・・・・。」
シオンは鋭く遠くを睨み付けた。
その横顔をイルは不安そうに見つめた。
「・・・じゃあ、私も一緒に行きます」
「え。いいよ、来なくて」
「足手まといだって言うんですか?急にロイア様を斬りつけたりしたら大変ですからね、見張ってます」
「なんだよそれ!来なくていいからっ」
「・・・ダメです」
ずいっと身を乗り出して、シオンのすぐ目の前にイルの顔がやってきた。
「お兄ちゃんの言うこと、ききなさい」
「・・・・・・」
しばらくきょとんとしていたが、やがてシオンは苦笑してから立ち上がった。
「わーったよ!ついてくりゃいーだろ!」
そのまま足早に歩いていってしまうシオンに、イルも慌てて立ち上がりついていった。
王宮に向かう二人は、小さく同時に呟いた。
「「・・・お兄ちゃん、か・・・」」
「・・・・・・おい」
「・・・・・・。」
セレナードの南部、カノンの近くの海が見える丘。
墓石の前で、リムは座り込んで泣いていた。
その後ろからサビクが歩いてきて声をかけたが、リムはただ泣き続けているだけだった。
「・・・そんなに毎日泣いてたら目がなくなっちまうぞ」
「・・・ひっく・・・・・・うう・・・・・・」
「ブラムさんが呼んでる。早く行かないと」
「・・・・・・ラスア・・・・・・」
「・・・・・・。」
ふう、とため息をついてサビクはしゃがみ込んだ。
リムの顔を覗き込んだが、手が邪魔でリムの顔は見えない。
「・・・おい、リム・・・」
「・・・かないで」
「え?」
「ブラムさんのとこ、行かないで・・・」
やっとしゃべったと思えば何を言うんだ、とサビクは顔をしかめた。
「俺たちが何のために頑張ってんのか忘れたのかよ。兄貴の仇を取るためにも俺たちは・・・」
「どうだっていいよそんなの」
「は・・・?」
泣いてしゃくりあげていた動きを止めて、リムは静かにそう言った。
「ど、どうだっていいって・・・」
驚いて、サビクはリムの両肩を揺すった。
「兄貴が殺されたのに、どうだっていいっていうのか?!」
「そうだよ!!どうだっていいよ!!そんなのもうどうでもいい!!」
リムの高い声が辺りに響いたかと思うと、サビクは突然抱き締められた。
サビクは何が起こったのか分からなかった。
「いやだよ・・・ブラムさんの言うこときいてたから、ラスアは殺されちゃったんだよ・・・?」
「・・・・・・お、おい」
「サビクまでいなくなっちゃったら、ぼく・・・どうしたらいいの・・・?やだよ・・・いなくならないで・・・」
「・・・・・・。」
リムにそんなことを生まれて初めて言われたので、
サビクは言葉を返せず、ただ口をぱくぱく動かすしかできなかった。
「お願い・・・ラスアみたいにならないで・・・一緒にブラムさんから逃げようよ・・・」
「リム・・・」
リムは、力いっぱいサビクを抱き締めた。
「もう絶対にバカって言わない!頭も蹴飛ばさない!何でも言うこと聞くから、お願い・・・!!」
「・・・・・・ははは」
リムの顔は自分の胸に埋まっていて見えなかったが、サビクは両手でリムの頭をポンと叩いた。
「リム・・・ありがとな。ほんと、ありがとう。今まで嫌味言ったり叩いたりしてゴメンな」
「嫌味言ったって叩いたっていいよ・・・何したっていいから、一緒にいようよ・・・」
「・・・・・・」
サビクは前に屈んで顔をリムの耳のそばまで近づけた。
「リム・・・ブラムさんと、約束したんだ。「大いなる存在」を生み出すまでは行動を共にするって。
・・・だから、行かなきゃいけない」
それを聞いてリムは目を見開いた。
そして上を向いてサビクに必死に訴えた。
「やだ!やだ!!行かないで!!お願い、サビク、大好きだから・・・行かないで・・・」
「・・・・・・」
リムの様子に、サビクは思わず苦笑した。
「・・・はは、どーしたんだよ。もう照れるからやめろって・・・」
「なんて言ったら、行かないでくれるの・・・」
「ごめんな。行かなきゃならないんだ。・・・でも、リムとも約束するよ。」
「・・・・・・?」
サビクを見上げて首をかしげたリムの目から、大粒の涙が流れた。
「絶対に死んだりしない。で、リムのことも絶対に守る。約束する」
「・・・・・・。」
「フレイ王子が大いなる存在を生み出したら俺たちの役目も終わりだ。俺たちがもう何かしなくてもいい。
大いなる存在の力さえあれば、そして王子ならば、この大陸の国を必ず平和にしてくれる。だから、それまでだよ」
リムは頷く代わりに、またサビクの服をぎゅっと握り締めた。
「フレイ、これは・・・?」
「・・・はい。どうぞ、受け取ってくださいトルライト様」
トルライトの私室の前。
フレイは、三つにたたまれた紙をトルライトに差し出した。
「・・・わかった」
「え・・・」
紙を開くこともなく、トルライトは目を閉じて頷いた。
その反応に、フレイの方が驚いた。
「トルライト様・・・」
「いつか、いなくなっちゃうんじゃないかってずっと思ってた」
「・・・・・・。」
「何も言わずにいなくなっちゃうかもって思ってた。言いに来てくれてどうもありがとう」
トルライトは立ち上がり、片手を差し出した。
握手を求めるトルライトの手に、フレイは手を出せなかった。
「・・・フレイ?」
「トルライト様・・・もしかして、全部分かってらっしゃるんですか」
「なにを?」
「・・・・・・。」
感情が読めない表情で、トルライトは微笑んだ。
「分からないよ。フレイが何がしたいのか全然分からない。でも、フレイの感情は分かるような気がする」
「・・・感情?」
「今までぼくの傍にいてくれてありがとう。もしも戻って来ようと思ってくれたらいつでも帰ってきてね」
「・・・・・・はい」
結局トルライトの手と握手することはせずに、深々と頭を下げてフレイは部屋から出て行った。
部屋に残されたトルライトは、その紙を開いた。
しかし中身も読まずに意味もなく四つ折にその紙を折り直して引き出しにしまった。
「よく、モデラートの王子がぼくと一緒にいてくれたよね・・・」
コンチェルト国の小さな村の宿屋の一室。
「・・・・・・」
ベッドに横になっていたイリスはゆっくりと起き上がった。
周りを見回そうにも目は見えないため、目を閉じたままだ。
「・・・おはよ、イリス」
頭の上から声がした。
それはイリヤのものだった。
「朝食できてるって。下の階に行こう」
手を差し出された気配がしたが、イリスはその手をとろうとしなかった。
イリヤはしばらく手を伸ばしていたが、イリスの様子を見てまた手を下ろした。
「・・・また、夢?」
「・・・・・・うん」
イリスは頷いて両手で布団を握り締めた。
「あの時、イリヤが私を助けに来てくれて今ここに隠れてるけど・・・もう王宮に帰らないと。このことを話さないと」
コンチェルトの王宮が急襲されたとき、イリスの部屋にも兵士が大勢やってきた。
しかしその兵士の中にイリヤも扮装して潜んでいたため、イリスは無事にイリヤに助けられたのだった。
「は、早く、イルとシオンに・・・・・・」
「もういいよ、イリス」
「・・・・・・え?」
イリスは、イリヤの声がした方を向いた。
「もう夢を見るの、やめよう。もう未来を見るのはやめようよ」
イリヤの言葉にイリスは思わずぽかん、と口をあけた。
「あはは・・・そんなの無理だよ。夢を見なければいいってこと?寝なかったら死んじゃうよ」
ふふっと冗談めかしく笑ったが、イリヤは笑わなかった。
「アルスが殺されること、イリスは知ってたんでしょ?」
「・・・・・・」
「その未来を何度も見たんでしょ?・・・けど、何も変わらなかったんでしょ」
「・・・・・・そうだよ」
消え入りそうな声でイリスは言った。
「アルスが殺される夢は、何度も見た・・・何とかしてアルスが殺されたときの様子が現実に起こらないように、
アルスをメヌエットの兵士と接触させないように、天授力を人に見せないように、言ってきたんだけど・・・」
イリスは布団を離して両手で顔を覆った。
「でも、だめだった・・・同じ夢を見るし、アルスにはとても言えなかった・・・そして夢のとおりになった・・・。
だから、これだけはみんなに伝えないといけない・・・このままじゃ、もしかしたらこの世界が・・・」
「もう、いいって。イリス」
イリヤはまた手を伸ばし、少し行き場に迷った後、イリスの頭の上に手を優しく置いた。
「その夢のことは忘れて。今すぐは無理でも、時間をかけて忘れよう」
「なっ・・・・・・」
なんてこと言うの、と言おうとしたが驚きのあまり声が出なかった。
「分かる?イリス。イリスが未来を見ようと見まいと、未来は変わらないんだよ。未来を見られても、未来は変えられない。
辛い未来をイリスだけが見て苦しむなんておかしい。・・・・・・ねえ、イリス」
イリスの頭から手をずらして、頬に触れた。
「・・・イリスが苦しむところ、悲しむところをぼくはもう見たくない。イリス、その天授力を消して」
「けっ・・・消す・・・?」
「できるんでしょ?自分からその力を放棄することが。自分で願えば、力を捨てられるんでしょ」
「・・・・・・」
イリスは唇をかんだ。
それを見てイリヤはイリスから手を離した。
しばらくしてイリスは軽く息を吐き出してから、顔を上げた。
「・・・できる・・・でも、そんなことをしたら・・・「メルディナを最善に導く力」を私が放棄したら・・・」
「よかった」
イリヤは急に明るい声でほっとしたように言った。
「イリス、生まれてからずっとぼくたちは一緒だよね。これからも一緒にいる。イリスのことを絶対に守る。
予言の力を失っても、ぼくが傍にいる。だからさ・・・未来じゃなくて、今を見ようよ。ぼくと一緒に」
イリヤの言葉に、イリスはまた言葉を失った。
思わず、目を見開いてイリヤの声がする方に顔を向けた。
「・・・そんな風に言われたら、絶対にイヤだなんて言えないじゃない。ずるいよ」
「え・・・」
「じゃあ、私からもお願いがあるから聞いて」
「な・・・なに?」
何を言われるのか想像がつかず、息を呑んだ。
「・・・プレイボーイはもう、廃業してくれる?」
「・・・・・・。」
イリスは笑いながらそう言い、イリヤは目を瞬かせた。
自分の様子が見えていないイリスに対してとにかく返事をしないと、喉から何とか声を絞り出した。
「もっ・・・・・・もちろん、イリスが・・・言うなら・・・・・・」
それを聞いて、イリスはまた目を閉じた。
両手を祈るように握り締め、下を向いた。
「・・・古の、遠き世界の癒しの司クレール様・・・」
イリスがそう言うと、イリスの体が淡く輝いた。
どこからともなく弱い風が吹いて、イリスの髪を揺らした。
「どうぞお許しください・・・私が授かったメルディナを最善に導く力、お返しいたします・・・」
イリスの体から光が溢れ、そして弾けて辺りに散らばり消えていった。
光が収まる頃に風も止まり、イリスの長い髪はふわりと肩の上に落ちた。
「・・・・・・!!」
突然、イリスが両手を顔に当てて、がばっと下を向いた。
「イリス!?」
驚いてイリヤはイリスの肩を支えた。
恐る恐る顔を覗き込んだが、イリスはぎゅっと強く目を瞑っていた。
「ど・・・どうしたの・・・?大丈夫・・・?」
「うん・・・あの、急に・・・眩しくなって・・・」
「えっ・・・!」
イリスは、薄っすらと目を開いた。
それでも眩しそうに顔を歪めていた。
その様子を、イリヤは固唾を呑んで見守った。
「・・・な・・・なにか・・・見える・・・?」
半分ほど目を開け、イリスの紫色の瞳がイリヤに向けられた。
イリスはイリヤを見つめたまま、微笑んだ。
「うん」
「ほんと・・・!?」
「私の・・・一番大切な人が、見えるよ」
「・・・・・・!」
イリヤは目を丸くして、さらに顔を真っ赤にして硬直した。
「そ、そ・・・そう・・・・・・奇遇だね・・・・・・」

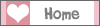
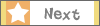
|