
そして、その日の夜遅く。
レインの部屋の窓からは城下町も見えるが、町の明かりはほとんどついていない。
「リム、そこにいても大丈夫?」
ラスアは胸につけているメダル、コムコインに向かって話しかけた。
メダルからはリムの声が聞こえてくる。
「平気ー、レインはまだ?って言うかさぁ、レインがいない内に逃げ出すのが一番安全なのにぃ」
「・・・ええと・・・レインさんが、大切なお話があるから待っててほしいって仰ったから・・・ごめんね」
「はあ〜・・・いいよ、そりゃ寂しいよね女の子が好きな人と会えなくなるのはさぁ」
「話し終わってレインさんがお休みになったら、すぐにこの窓から降りるから。待っててね」
「うん・・・・・・あっ!!」
「えっ?」
メダルからリムの大きな声が聞こえてきた。
「そ、そんなに大声出して平気・・・?誰もいないの?」
「もうほとんどの人寝ちゃってるもん・・・門番からもすごく遠いしここ・・・そ、そうじゃなくてさ」
「どうしたの?」
慌てた声のリムを落ち着かせるようにラスアは優しく言った。
「その・・・王様にいじわる言われて怒ってそのまま出てきちゃったから・・・」
「・・・え?」
「その〜・・・ぼくのベッドの下に、天秤置いたまんまだ・・・あははは〜・・・」
「ち、ちょっと!あははじゃないって!」
なんとリムはベッドの下にホロスコープを隠したまま忘れて城から出てしまっていた。
ラスアはコムコインを片手で持ったまま、リムが使っていたベッドの下を覗きこんだ。
「ええと・・・暗くてよく見えないなあ・・・」
「あ、あった?掃除されちゃってない?」
「うーん・・・・・・あ、あったあった!」
「よかったぁ・・・」
「じゃあ、私が抜け出す時に忘れずに持っていくから。じゃあそれまでリムも、そこで待ってて。寝ちゃダメだよ」
「分かってるよぅっ!」
リムの反論に ふふふ、と笑いながらラスアはコムコインの通信を切った。
そして、窓の外を見上げた。
丁度ラスアが見ている窓の下の地面にはリムがいるのだが、この部屋が高い階にあるのと真っ暗なため見えない。
「・・・安全に、ホロスコープを持って抜け出さなきゃ・・・」
ラスアは振り返って、リムが使っていたベッドの方を見た。
「・・・ば、バルゴさん・・・お休みですか・・・?」
リムと話し終わってから数十分が経過した。
自分の部屋なのだが遠慮がちにレインが扉をそっと開いた。
「バルゴさん・・・・・・」
レインが寝ているベッドとラスアが寝ている場所は仕切られていて、ラスアのベッドの方が部屋の奥にある。
ひとまず自分の今日の仕事道具もとい筆記用具をまとめてテーブルの上に置いて、
ラスアが寝ているであろう部屋の奥まで忍び足で歩いていった。
「・・・・・・」
部屋の奥の大きな鏡の前で、ラスアは立っていた。
起きていたことに安堵して、レインは普通に歩いてラスアに近づいた。
「バルゴさん?明かりもつけずに、どうなさったんですか?」
部屋は星の明かりで照らされているだけで、物の色を判別するのは難しいぐらいに薄暗い。
「起きて下さっていたんですね・・・お疲れだったでしょうに、ありがとうございます」
「・・・い、いいえ・・・」
レインの方に振り返ろうとせず、やっとラスアは口を開いた。
「レインさんこそ・・・お疲れでしょう。夜遅くまでご苦労様です」
「大丈夫ですよ、明日から休暇ですから。」
「そうなんですか・・・」
「あ、そう、それで・・・なんですけど・・・」
本題に入るため、レインは手を後ろに組んだ。
「わ、私、本気でバルゴさんをお慕いしています。それで、バルゴさんを・・・」
「違うんです!!」
「え」
ラスアはレインの言葉を遮り、突然振り返った。
「な・・・なにがちがっ・・・」
「私っ・・・私の本当の名前、バルゴじゃないんです!私の本当の名前は・・・」
泣きそうなラスアを見て、レインは言葉を詰まらせ硬直した。
「私の名前・・・本当は、ラスアっていうんです・・・」
「・・・ラスア?」
「ごめんなさい・・・ごめんなさい、ずっと、言えなくて・・・騙していて・・・ごめんなさい・・・!!」
ラスアは両手で顔を覆って泣き出してしまった。
「何を・・・何で泣くんですか・・・?バルゴさん・・・あ、ラスアさん?私、言ったじゃないですか。」
ラスアの両肩を、レインは両手で支えた。
レインよりラスアの方が背が高いため、少し上向きになっている。
「私は貴女がどんな人でも構わないと。どんな人だって私にとって大切な人だとお伝えしたばかりでしょう?」
「・・・・・・!」
その言葉にラスアは目を見開いた後、また再び泣き始めた。
「一生話さなくてもいいと言ったのに・・・話してくださってありがとうございます。もう十分ですよ」
「・・・レイン、さんっ・・・」
「私には貴女がいて下さればそれでいい。だから明日、私の実家に・・・同行してくださいませんか?」
「えっ・・・」
ラスアは顔を上げた。
泣き腫らした目を見てレインは苦笑した。
「ラスアさんを家の者に紹介したいんです・・・・・・ね、そんなに泣かないで下さい」
そう言ってレインは胸ポケットに入っている薄い青色のハンカチを取り出してラスアの涙を拭いた。
ラスアはそのハンカチを受け取ってぎゅっと握り締めた。
「はは・・・こんなにまた貴女を泣かせて・・・リムに怒られちゃいますね・・・」
レインは涙を拭っているラスアを見ながらまた笑った。
「・・・ラスアさん、一緒に来てくれますか?明日、私の家に。リブレット家に、貴女をお迎えしたいんです」
「・・・・・・・・・。」
ラスアは、今度は泣きそうではないがものすごく辛そうに、顔を歪めて唇を噛んだ。
「・・・・・・ラスアさん?・・・わっ」
突然飛びつく様にラスアに抱きつかれて、レインは少しよろけた。
顔を見ることはできなかったが、代わりに静かにラスアの声を待った。
「・・・・・・私も、レインさんのことが、大好きです・・・」
ラスアの声が、絞り出すように聞こえてきた。
「大好きです・・・愛しています・・・世界中の誰よりも何よりも、一番大切なのはレインさんです・・・」
「・・・・・・。」
「・・・一生、レインさん以外の人は愛しません・・・」
そして、レインを力の限り抱き締めた。
ラスアのことを、レインも抱き締め返した。
「・・・・・・その言葉を頂けて嬉しいです。」
長い時間抱き締め合っていたが、レインの方から腕を解いた。
少し目線を上にして、ラスアに向かって微笑んだ。
「では、明日の朝早くに出たいと思っていますから。もう今日は休みましょう。ね」
レインは自分のベッドの方に向かい、着替え始めた。
後姿を目で追っていたラスアだったが、ぱっと顔を逸らして自分のベッドに座り込んだ。
レインが寝る支度を整えて「おやすみなさい」と言ってそれに返事をするまで、ずっと床を見つめていた。
「ふあ〜あ・・・」
目尻に涙を溜めながら、リムは両手を上げて大あくびをした。
ラスアと通信を切ってから一時間近くになるが、もう真夜中になっていてリムの眠気はそろそろ限界に近づいていた。
「ねむーい・・・・・・ん?わっ?!」
伸ばしている片手に何かが触れ、リムは慌てて手を引っ込めた。
布に手が当たったらしい。
「・・・え?あれ?ねえ・・・きみ、ホロスコープの・・・バルゴ、だよね?」
なんとリムの横にはバルゴが座っていた。
リムの問い掛けに答えて、バルゴは柔らかく微笑みながらこくこくと頷いた。
「あ、しゃべれないんだっけ・・・・・・あのさ、ずっとここにいたの?」
バルゴはまた頷いた。
「あの窓から降りてきたの?」
そう言って、レインの部屋の窓を指差した。
バルゴは上を見てから、リムに向き直って頷く。
「・・・ってことは、ラスアが天秤のホロスコープを体に入れるために、元々入ってたバルゴを出したのか・・・」
リムが考えている間、バルゴはリムの顔を何も分かっていない表情で見ているだけだった。
ただ、可愛らしく微笑んではいる。
「・・・あのぅ、そんなにニコニコされても・・・ぼくも今ホロスコープを一つ体に入れてるから、バルゴは入れられないんだ」
バルゴを入れたらぼくが乙女になっちゃうしね、とリムはバルゴに言い聞かせた。
「あ・・・来た来た、ここだよラスア!」
壁を蹴る音がしたためまた上を見ると、丁度ラスアが細いロープを使って窓から降りてきているところだった。
二重になっているロープを伝って降りてきたラスアは、持っていた部分の結び目を解いて長いロープを回収した。
ラスアの表情は見えなかったが、リムは覗き込もうとはしなかった。
「レインとのお話終わったの?」
「・・・・・・うん」
「天秤のホロスコープは?」
「ちゃんと体に入れてあるよ。バルゴ、先に行かせちゃってごめんね」
バルゴは微笑んだまま首を横に振った。
「・・・じゃ、とりあえずこの王宮から離れよう。行こう、リム」
「はぁい」
ラスアを先頭にして、リムとバルゴは後ろからついて行った。
「・・・・・・。」
窓の方を振り返ろうと一瞬考えたが、ラスアは目を細めて首を振った。
次の日の朝。
メヌエットの王宮の、外に出るための庭に続く門に向かってレインは歩いていた。
「レイン」
後ろから呼びかけられ、その声にレインは振り返った。
いつもはいるお供の人が左右におらず、ロイアが一人で立っていた。
「ロイア様・・・」
「今日からしばらく休暇だな。家まで気をつけて行けよ」
「お気遣いありがとうございます、外に馬車を待たせてあるので大丈夫です」
「そうか」
そう言いつつ、ロイアがレインに歩み寄ってきた。
「ロイア様?」
「・・・一緒に連れて行くんじゃなかったのか?あの女はどうした?」
「・・・・・・。」
レインは、目を逸らして荷物をぎゅっと握り締めた。
「・・・深夜、出て行かれました。窓から・・・」
「止めなかったのか?」
「止めても無駄だったと思います。昨日お話しして分かりました・・・私にできるのは、あの方を見送ることだけでした」
「・・・そうか」
ロイアは腰に手を当てて苦笑しながら ふう、と息を吐き出した。
「落ち込むなよ。だから最初に言っただろう?仕事に支障をきたすんじゃないぞ」
「はい・・・もちろんです」
「それに」
声を小さくして、ロイアはレインにだけ聞こえるように言った。
「今だから言うが・・・あいつは男だ。」
ロイアの声に、レインはこれでもかと目を大きく開いた。
「何考えてるか分からんだろ・・・危なかったな、レイン」
「・・・・・・ますよ」
「・・・え?」
下を向いたまま、レインはロイアよりも小さな声で言った。
「知ってますよ。分かってましたよ、あの方が男性だと。バルカローレに行っている途中で気付きました」
「えっ・・・!?そ、それじゃ・・・」
「私はあの方を、ラスアさんを本気で愛したんです。それだけです。お気遣いありがとうございますロイア様」
途中までは真面目な表情だったが、ロイアに向かってお辞儀をしてからはいつものように笑っていた。
「それでは失礼いたします。大丈夫です、ちゃんと帰ってきたらバリバリ働きますから!では、行ってきますっ!」
ガッツポーズをして見せた後、レインは広い庭を走り抜けて行った。
残されたロイアはリアクションする暇もなく、ただ呆然としていた。
「・・・・・・あ、うん。気をつけて・・・」

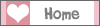
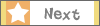
|