
シオンは目を瞬かせた。
「ロイアは「二冊で一つの意味を持つ」って言ってたんだけど・・・だから、それ貸してもらえないかなって、思ってたんですけど・・・」
「うーん・・・どうしよう」
トルライトは本の表紙を見ながら悩んだ。
「どうして先王は、二冊そろえちゃいけないって言ってたんだろう・・・?」
「分からない・・・セレナードがモデラートを統合した時、ぼくの父上の父上の父上の・・・つまりおじいさまのおじいさまから伝わってるんだって」
「へえ・・・」
「ぼくの父上よりも前の人たちは、王にはならなかった人が多いんだけどね。でも代々この本は特に大事になさっていたんだって・・・」
「・・・・・・。」
ロイアに藍の伝承書を探せと言われていたが、これでは持って帰るのが難しそうだ。
「とりあえず、本の中身見せてもらってもいいですか?」
「いいよ。ぼくは読めないんだけど・・・」
シオンはトルライトから本を受け取り、適当なページを開いた。
フレイも後ろから覗き込んだ。
「・・・うー、やっぱ読めないか・・・なんだこれ」
ページをぱらぱらとめくったが、シオンには理解不能な文字が並んでいるだけだった。
「・・・癒しの願い・・・自然治癒力を急激に高める・・・」
「へ?」
後ろからフレイの声がして、シオンは驚いた。
「よ・・・読めんの?」
「この部分だけ・・・なんか、読めるみたい・・・悠久の響きを知る力・・・星座の統率・・・天授力に関するページかな・・・」
「フレイすごいな・・・えと、じゃあこのページは?」
シオンはどうせなら最初から読んでもらおう、と1ページ目をめくった。
そのページにフレイは目を通したが、唇をかんで首を横に振った。
「藍の伝承書、っていう文字しか分からない・・・ごめん、やっぱ読めないみたい」
「いや、すごいって・・・癒しの願いって、イルの天授力のことだよな?」
「そうだと思う・・・」
「ビアンカ様は茜の伝承書は読めたみたいだけど・・・こっちの藍の伝承書は読めるのかな・・・」
シオンとフレイが うーん、と考えていると、トルライトは別の意味で首をかしげた。
「ビアンカ様って・・・クーデターで追放された、あのビアンカ王子?」
「あ・・・・・・」
二人はしまった、と顔を見合わせた。
「えーと・・・隠しておくべきかも分からないんだけど・・・ビアンカ王子、生きてるんですよ」
「え?そうなの?!どこかの牢屋に?」
「いや・・・普通に、コンチェルトで暮らしてて・・・」
「ええっ!?」
狭い書斎に、トルライトの声が響き渡った。
「声 でか・・・」
「ビアンカ王子、生きてたんだ!よかった・・・!!そうだよね、ロイア王子さすがっ・・・!」
トルライトは書斎の机にぶつかりながらも喜びのガッツポーズを繰り返した。
「危ないですよ王様・・・」
シオンは怪我しないか、と心配して本を片手で持ってもう片方の手をトルライトに伸ばした。
その時。
「トルライト様!カペルマイスター!!」
書斎の半分開いている扉から声が聞こえた。
「なに?」
トルライトは両手を握り締めたまま、扉の外にいる人に顔を向けた。
「マラカ様が、カペルマイスターをお呼びです。」
「ぼくを?じゃあ行ってくる・・・」
「あ、ああ・・・分かった」
シオンは部屋から出て行くフレイに手を振り、そしてトルライトに向き直った。
「・・・あの」
「どうしたの?」
書斎に二人きりになり、シオンは遠慮がちに頬をかいた。
「普通・・・王様を余所者と二人だけにしない・・・ですよね?大丈夫なんですか?」
「いいのいいの」
トルライトは右手を立ててパタパタと振った。
「王なんていてもいなくても同じだもの。元老院が全部決めちゃって、ぼくは承認するだけ。一応拒否権もあるけど・・・」
「え、でも・・・だから俺、部外者で、今日初めて会ったのに・・・」
「それはぼくがいいって言ったから。」
「へ?」
シオンの腕をぽん、と叩いた。
「ぼく、決めたらすぐに行動するタイプなんだ。フレイをカペルマイスターにしたのも、突然決めたんだよ」
「・・・・・・」
「ぼくはシオンのこと、なんだかすごく信頼できるって思った。セレナードにずっといてもらいたいって思うぐらいに」
「えっ・・・!そ、それは・・・どうも・・・」
シオンは照れて思わず頭を下げた。
しかし、セレナードにずっといることはできないな、と内心残念に思った。
「そういえば」
トルライトがシオンの手にある藍の伝承書をめくった。
そして、真ん中より少し後のページを開いた。
「なんですか?」
「このページなんだけど・・・破られてるんだよ、ここがほら」
「あ・・・・・・!」
トルライトが指差す本の真ん中部分は、破り取られていた。
「本当だ・・・ビアンカ様の本と同じ・・・」
「ビアンカ王子の本?同じって、どういうこと?」
「ビアンカ様は、先王ケッセル様から茜の伝承書っていう本を受け継いでいらっしゃって・・・」
「茜の伝承書・・・これは青いけど、その本は赤いの?」
「はい、それで、その茜の伝承書も破られた跡があって・・・」
「・・・ふーん」
本を何気なくめくりながら、トルライトは軽く頷いた。
「誰が破ったんだろう・・・?何のために?そもそもこの本は誰が書いて、伝わってるんだろう・・・」
「全然分からないです・・・でも、茜の伝承書はビアンカ様、読めるんですよ」
「そうなんだ・・・!じゃあこの藍の伝承書も、読んでもらえないかな・・・」
シオンは はっとして、本を閉じた。
「こ、この本、持ってっても・・・いいですか?」
「・・・・・・」
思い切って、尋ねてみた。
トルライトは難しい顔をして、下を向いた。
「うーん・・・父上の言ったことは守りたいけど・・・ぼく自身、その本の謎は知りたいし・・・どうしよう」
「・・・あの、ここ数年で、よく・・・事件が起きてますよね?」
「事件・・・?」
シオンは、藍の伝承書を持っていきたい理由を話すことにした。
「動物に襲われる事件が・・・増えてるでしょ?その原因を知るためにも、二冊の伝承書が必要なんですよ」
「動物に・・・セレナード以外でも、起こってるの?」
「この前もコンチェルトで動物に一つの集落が襲撃されたそうです。俺も、ここに来るまでに狼に襲われたし・・・」
「・・・・・・」
トルライトはシオンから視線を逸らして黙ってしまった。
何かを必死に考えている様子だ。
「とにかく・・・その二冊が揃わないと、事態が進展しないんですよ・・・分からない事だらけで・・・」
「・・・うん、わかった」
目だけをシオンの方に向け、トルライトは頷いた。
「えっ?」
「わかった、いいよ。その藍の伝承書、貸してあげる。」
「い・・・いいんですか?!」
「シオンがこの国を出る日に、持たせてあげるよ。普段はこの書斎に隠しておかないといけないから」
そう言ってトルライトはシオンの手から本を取り、本棚の裏の隠しスペースにしまった。
「帰る日に、ここからまた出すね。それと・・・一応、マラカにも言ってからじゃないと・・・」
「分かりました・・・あ、ありがとうございます」
「ううん、ぼくが決めたことだから。いいよ」
本棚に最初から入っていた本を詰めて、隠し場所が見えないように戻した。
そしてトルライトが後ろで腕を組んで、シオンに向かって笑ったとき。
「シオン・・・まだここにいる?」
「ん?」
書斎の外から声が聞こえた。
それはフレイのものだった。
「フレイ?どうした?なんのお呼び出しだったんだ?」
「その・・・いや、公的な話じゃ・・・ある意味公的かな・・・ちょっと、一緒に来てくれる・・・?」
「いいけど・・・あ、トルライト様、またあとで」
「うん・・・」
何となくおろおろしているフレイの後ろからシオンは何のことはなしについて歩いた。
「あの・・・じゃ、ぼくはこれで・・・」
「おい、フレイ?どこ行くんだよ」
「・・・・・・。」
部屋の前まで連れてこられたシオンは、フレイの背中に呼びかけたがフレイはとっとと角を曲がって行ってしまった。
首を傾げつつ、シオンは扉のノブを捻った。
「お邪魔します・・・?」
またやたらと広い部屋だった。
真ん中に大きな長椅子が置いてあり、左右には大きな窓がある。
その窓には一人ずつ、お城の使用人が立っていた。
そして、シオンの目の前には。
「シオン、よく来てくれました」
「・・・・・・はい?」
手を後ろに組んで微笑んでいる、マラカ姫が立っていた。
シオンはきょとん、としてマラカを見下ろした。
「なんだ・・・?あ、なん・・・ですか?」
「シオンの役目は私をセレナードに送り届けること・・・でしたわね?」
「は・・・はあ、そうですけど」
マラカが部屋の奥に向かって歩き出した。
何となく、シオンもその後ろをゆっくりとついていった。
「それが無事に終わった今・・・どうするつもりでいますの?」
「えー・・・」
マラカは ぴた、と歩く足を止めた。
返事に困ってシオンは窓の近くにいるマラカの世話係であろう人物を見たが、特に反応は得られなかった。
「もう、すぐに・・・コンチェルトに帰るのかしら?」
「・・・・・・」
何でそんなことを言われるのか、シオンはサッパリ分からなかった。
「・・・まあ・・・一応、そのつもりですけど・・・」
ジェイドミロワールを置くというビアンカの頼みも達成できたし、もうこの国でやることはなかった。
アルスも待っているし、早くコンチェルトに帰りたいというのが素直な気持ちだ。
「・・・・・・。」
今度はマラカが黙ってしまった。
後ろから見ているので顔は見えないが、そのままマラカは下を向いてしまい、シオンは少し慌てた。
「・・・あの?」
「座って・・・くれない?」
「・・・・・・はい?」
マラカは下を向いたまま、大きな椅子に座った。
右半分を空けて座ったため、どうやらそこにシオンに座ってほしいらしい。
散々戸惑った挙句、シオンは大人しくマラカの横に座った。
「・・・あのー・・・どうしたんです?」
マラカの顔を覗き込むようにシオンは顔を傾けて話しかけた。
しかしマラカの髪に阻まれて、表情を見ることはできない。
「・・・帰らないで・・・」
「へ?」
「いやだ、帰らないで・・・!ずっとセレナードにいて・・・お願い・・・!」
「?!」
突然マラカは顔を覆ってさめざめと泣き出してしまった。
シオンは更に狼狽した。
「ど、ど、ど、どうしたんです?!な、なんで?!ちょっ、な、泣かないで・・・!!」
背中を支えてもいいのか、つまり触ってもいいのか分からず、シオンの手は宙を彷徨った。
部屋にいる人の視線を一瞬気にしたが、ついに構わずシオンはマラカの背に手を当てて顔を覗いた。
「なんで・・・?急に泣き出されても・・・どうしたん・・・です、か?」
「・・・・・・っ」
マラカは答えず、顔を覆ったまま首を左右に振るだけだった。
ひとまず落ち着かせようと、シオンはマラカの肩と背を優しく叩いた。
しばらく泣き続けていたが、マラカはようやく泣き止んだ。
両目をごしごしと手でこすり、しゃくりあげている。
そして、シオンの手を片手で握った。
「・・・・・・!」
「シオンからしたら私なんてただの子供かもしれないけど、でも私、ずっとシオンといたい・・・」
そう言うマラカは確かに小さな子にしか見えないが、シオンを見つめる目は本気だった。
シオンは、突然泣き出したときよりも更に混乱した。
「・・・え、あ、あの・・・」
「どこにも行かないで、ずっと私の側にいて!シオンを他の誰かになんて渡したくない!」
「・・・渡すって」
物か、と思いつつもシオンはとりあえず落ち着こう、とクールダウンを試みた。
「えー・・・王女、俺のどこが気に入ってもらえたんです?」
「とてもかっこいいわ。優しいし」
「そう・・・ですか」
割と子供らしい答えが返ってきてしまった。
何か優しいことしただろうか、と回想したが何も出てこなかった。
しかし容赦なくマラカは続けた。
「私、立派な、素敵な女性になる。どこにも行かないで。お願い」
「うー・・・」
シオンはマラカに握られている方の手ではない方の手で自分の頬を支えた。
「ご存知だと思いますけど、俺はコンチェルトの王宮剣士で・・・」
「トル兄様にお願いして、もっともっと良い地位をあげるわ。」
「でも俺には弟がいて、コンチェルトで待ってるんですよ」
「弟さんも一緒に来たらいいわ。シロフォンに一緒に住めるようにして差し上げるから」
「・・・うー・・・」
どうにも諦めてもらえないようで、シオンは更に悩んだ。
「・・・それとも、もう心に決めた方がいるの?」
マラカが、ふとシオンの手を放した。
「それなら・・・仕方がない・・・けれど・・・」
「あ、ちょ、ちょっと!」
また泣き出しそうになったマラカに、またシオンは慌てた。
口調は大人びているが、すぐ泣き出すところは全く子供である。
「どうしよう・・・」
シオンの心の叫びが、聞き取れないぐらい小さな声で思わずシオンの口から出た。
しかしマラカはまた泣き出すことはなく、悲しそうに顔を歪めただけだった。
「・・・じゃあ、3年・・・」
「え?」
「あと3年すれば、私も結婚できる年齢になるから・・・その時に、シオンに好きな人がいなければ・・・」
「いなければ・・・?」
結婚してくれ、とでも言うのかとシオンは身構えてしまった。
「私のこと・・・思い出してほしい・・・」
「・・・・・・。」
縋るような目で見られて、思わずシオンは心なしか頬を染めて目を逸らした。
この少女の必死の告白を無碍にすることはできず、シオンはマラカの肩を軽く叩いて微笑んだ。
「・・・ありがとうございます、王女。光栄です」
「・・・・・・。」
「でもこれから先、もっとマラカ様に相応しい人が現れるかもしれません。その時は、是非その人を愛してあげてください」
言っていて、シオンは少し気恥ずかしかったがそんなことを考えている場合でもなかった。
「3年後、王女が言ったような条件の状態なら・・・俺は、またここに来ます。お約束します」
「・・・本当?」
「その時は王女は美しく成長なさってて、俺の事なんか相手にしてくれないかもしれないけど」
「絶対、そんなことない。私の気持ちは変わらないから」
「・・・はは、ありがとうございます」
確信を込めて言うマラカの幼い顔が可愛くて、シオンは苦笑した。
そして、思わずいつもアルスにするように頭をぽんぽん、と撫でた。
「あっ・・・やっぱり、子供扱いしてる」
「そ、そんなことないです、ごめんなさい・・・」
ぱっと手を引っ込めたとき、部屋にはマラカの世話係の人がずっといたことを思い出した。
素早く椅子から立ち上がり、軽く一礼した。
「あの・・・じゃ、失礼します・・・」
そして逃げるように部屋を後にした。
マラカは椅子に座ったまま、扉が閉まるまでシオンを見送っていた。

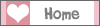
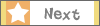
|