
「・・・ローチェ、もうダメみたい」
かすかに聞こえるだけの小さい声で、クラングは言った。
「クラング?」
「もう髪が・・・時間切れだね」
「・・・そうか、でもあと少しでここから出られるわけだし・・・」
「・・・・・・。」
クラングは、床に座り込んで下を向いた。
「ローチェ・・・」
「なに?」
「一つだけ教えてほしいことがある」
「・・・クラングに教えることなんてないだろう?」
ずっと一緒にいたんだから、とローチェは呆れた。
とりあえず、クラングの言葉を待った。
「一番大切なものは・・・王子だよね?モデラートだよね・・・?」
「・・・・・・!」
ローチェは目を見開いた。
クラングの顔は、下を向いていて髪に覆われているので見ることができない。
しばらく黙った後、目を閉じて頷いた。
「・・・ああ、当然だ」
「・・・・・・そうか、よかった。」
クラングは顔を上げ、小さな窓を見上げた。
「・・・ちょっと、不安だったんだ」
「分かってる・・・・・・・・・けど」
ローチェが何かを言いかけたとき、少し遠くから兵士の声が聞こえた。
「おい、時間だ。出ろ」
牢屋の鍵が二つとも開けられて、重い扉が開いた。
そして二人は、各自二人の兵士に挟まれて牢屋から出て行った。
「あっ・・・いよいよ出てきますよ」
「何だか国賓扱いだよね」
道の形に並んでいる兵士達の間を、クラングとローチェはこれまた兵士達に囲まれながら歩き始めた。
みんな緊張した面持ちだが、イルだけはこの上なく嬉しそうだ。
「早く普通に生活できるようになったらいいですよね〜」
「でもイルは、バイエルをセレナードに送っていくんでしょ?」
「そうですけど・・・あっ!その間にローチェさんに近づいたら承知しませんからね!!」
「あはは、それは約束しかねるかな」
「なっ・・・!!」
クラングとローチェが通る空間を隔てて、イルはイリヤを睨みつけた。
しかししばらくすると、周りにいる人たちがざわつき始めた。
「あれ・・・」
「おい、あの二人・・・」
二人の姿が見え始めた時、イルも違和感を覚えた。
「・・・ローチェさん、髪の色が白いような・・・」
今まで暗い地下牢にいたから気づかなかったが、最初に見た時の髪の色と違う。
イリヤも首をかしげた。
「あれ・・・二人とも茶色の髪だったよね・・・」
そのざわめきが大きくなり、列を乱す兵士まで出てきた。
「あの二人、テヌートなんじゃないか?」
「テヌートだったのか・・・!?」
イルとイリヤからもクラングとローチェの姿が確認できるような位置に来た時。
突然、クラングが走り出した。
「えっ?」
イルはローチェに渡そうと思っていた花束を握り締めて、後ずさった。
クラングはイル目がけて走っていた。
「・・・・・・!!」
それを見て、ローチェも走り出した。
二人とも、イルの方向へ走ってきている。
二人の兵士が立ちふさがって止めようとしたが、クラングは二人の肩を両手でついて飛び上がった。
ローチェは二人の間を身を屈めてすり抜けた。
クラングが着地した地点にいた兵士の剣を素早く引き抜き、クラングはその兵士を後ろに蹴り飛ばした。
「言ったよね、天授力を持つ人間は殺すって」
イルの方に振り返り、クラングは静かにそう言った。
「くっ、クラングさん・・・」
兵士の横からの攻撃を軽くなぎ払い、イルに向かって剣を振り上げた。
「イル!!」
イリヤは自分の剣を抜き、クラングに向けて駆け出した。
その他、周りにいた兵士達も遅れて剣を抜いて駆け寄った。
花束を持った手を、イルは思わず顔の前で交差した。
すると、その花束はクラングの振り下ろした剣によって切り裂かれて空中に散らばった。
斜め横に振り下ろした剣を再び横に振り上げ、今度はイルの首を目がけて振り下ろした。
「・・・・・・!?」
思わず目をつぶったイルだったが、何かにぶつかる衝撃を受けて後ろに倒れこんだ。
それと同時に、兵士の一人の剣がクラングの背を貫いた。
「うっ・・・!!」
クラングは剣を地面に落とし、膝をついた。
そして、イルの目の前には。
「・・・ローチェさん・・・・・・!!」
ローチェが、イルに覆いかぶさるように倒れていた。
肩から腰にかけて、クラングの太刀による深い傷から大量の血が流れ出ていた。
「ローチェさん・・・わ、私を・・・」
「・・・すまなかった・・・どうしようも、なかったんだ・・・」
イルは両肘で上半身を支えている。
力が抜けているローチェを支えるのがやっとで、立ち上がることはできなかった。
「ローチェ・・・やっぱり・・・」
はっとして声がした方を見ると、クラングが兵士達の間で倒れていた。
何度も斬りつけられ、辺りは血だらけだった。
「やっぱり・・・庇うと思った」
「クラング・・・・・・ごめん・・・」
顔をわずかに上げ、クラングは笑った。
「ううん・・・・・・よかった・・・・・・」
そう言って、目を閉じて動かなくなった。
「クラングさん・・・!!」
イルは思わず呼びかけたが、もう返事はなかった。
イリヤが剣をしまって、クラングの側にしゃがみ込んだ。
「・・・テヌートが・・・なぜ・・・」
ローチェを抱きかかえて、イルは自分の天授力のことをやっと思い出した。
「ろ、ローチェさん、その傷・・・治しますから・・・!」
そう言って、ローチェの背に片手をかざそうとした。
しかし、その手はローチェの手によって止められた。
「・・・えっ・・・」
「どうせ助からない傷だ・・・もういい」
「そ、それなら、ビアンカ様がくださったシードがあれば・・・!」
「・・・もう、いい・・・」
ごほっ、と咳き込むと、ローチェの口から真っ赤な血が溢れ出た。
それを見てイルは目をこれでもかと見開いた。
「い、いやですっ・・・ローチェさん・・・わ、私は本当に、貴女をっ・・・」
「・・・ありがとう、イル・・・・・・嬉しかっ・・・た・・・」
ローチェは自分の指から指輪を抜き取り、イルの胸の上に指輪を持ったまま手を置いた。
そして、ゆっくりと目を閉じた。
「そっ・・・そんな・・・なんで・・・」
動かなくなったローチェを抱き締め、イルは体を震わせた。
「なんで、どうして・・・!ローチェさんっ・・・・・・!!」
目を見開いているのに、涙がこぼれて止まらなかった。
それから数日後。
クラングとローチェは共同墓地に埋葬され、城内も落ち着きを取り戻しつつあった。
しかし、イルはもう何日もろくに食事もとらず、部屋から出ることもなく落ち込んでいた。
「ねえ、アルス・・・」
「しっ、こっち来てバイエル君」
イルの部屋の中。
アルスはバイエルの世話に来ていたが、ここに来たのはもう一つ理由があった。
「うーん・・・困ったな・・・」
部屋の奥にいるであろうイルに聞こえないようにしたかったが、バイエルにそれを説明するのも難しい。
バイエルの手を持ったままおろおろしていると、突然無遠慮に扉が開いた。
「や、みんな元気?」
「い・・・イリヤさん」
明るい表情でイリヤが入ってきた。
そして、部屋を何気なく見回した。
「・・・イルは?」
「部屋の奥に、一人で・・・」
「そうかー・・・バイエル、ちょっとおいで」
「え?ぼく?」
「うん。お兄さんと遊ぼうね〜」
「・・・・・・。」
イリヤの物言いに若干不安になりつつも、アルスはバイエルをイリヤに渡した。
バイエルの背中を叩きながら、イリヤはとっとと部屋から出て行ってしまった。
なにするの?どこにいくの、というバイエルの声が外から聞こえてくる。
しかしその声もやがて部屋から遠ざかっていってしまった。
アルスはイルと二人っきりで話がしたかったのだからイリヤがとってくれた行動は正解だった。
だが、どう慰めの言葉をかければいいのか見当もつかなかった。
広間からは見えない、イルがいるベッドがある部屋にアルスはそっと近づいた。
「・・・・・・イルさん」
「・・・・・・。」
人の気配はするが、返事がない。
アルスは意を決して部屋に一歩踏み込んだ。
「イルさん・・・・・・」
イルは、床に座り込んでいた。
上半身はベッドにもたれかかって、うつ伏せの状態である。
「・・・あ、アルス・・・来てたんですか」
「すみません、あの・・・」
ゆっくりと顔を上げたイルを見て、アルスは言葉を詰まらせた。
イルの目が泣き腫らして真っ赤になっていたからだ。
「・・・イルさん・・・その、ぼく・・・・・・すみません・・・」
「・・・・・・。」
何か言おうとしたが、全く言葉が出てこない。
イルはベッドにもたれていた体を起こした。
「・・・アルス・・・?」
「ごめんなさいっ・・・ぼく、何も出来なくて・・・元気出してくださいって、言いたかったんですけど・・・」
イルの横に、アルスも座り込んでしまった。
「それだけしか言えないなんて・・・ぼく、イルさんが悲しんでるのにっ・・・何も出来なくて・・・っ」
「あ、アルス」
突然さめざめと泣き出してしまったアルスに、イルは慌てた。
「どっ、どうしてアルスが泣くんですか。わ・・・私が悪いんですから・・・」
「ごめんなさいイルさん・・・ごめんなさいっ・・・」
「・・・・・・。」
顔を両手で覆って、いよいよ本格的に泣き出してしまった。
慰めに来たはずのアルスを、イルが慰めることになっている。
「アルス・・・」
アルスが泣き出してしまってから、今までずっと泣き暮らしていたイルも泣くに泣けなくなっていた。
落ち着かせようとしたが、イルが何を言ってもアルスは首を横に振るだけだった。
アルスの横に座り込んで、アルスの背を撫でながらイルは窓の外を眺めていた。
そのまま1時間近く、二人は床に座り込んでいた。
そして、ようやく泣き疲れたのか、アルスが泣くのをやめて目をこすった。
「・・・・・・」
「だ・・・大丈夫ですか、アルス・・・?」
「・・・ごめんなさい、励ましに来たのに、ぼくがこんなに泣いちゃって・・・」
「そ、そんな、十分励まされましたよ・・・アルスがそんなに悲しまないで下さいよ・・・」
イルは視線を逸らしながら、頬をかいた。
「私・・・クラングさんとローチェさんがあんな風に死ななければいけなかったのは、自分のせいだと思ったんです。
余計なことをしなければよかったって・・・それで、もうずっとこのまま泣いていてもいいって思ってたんですけどね・・・」
そう言って、ずっと握り締めていたローチェの指輪を指でとんとん、と叩いた。
「何も考えたくなくて、何もしたくなかったんですけど・・・それじゃ、いけないって思いました」
「・・・・・・」
立ち上がって、指輪を机の上に置いた。
「私、あの二人を殺した人を探し出します」
「えっ・・・?」
突然聞こえた思いがけない言葉に、アルスは思わず顔を上げた。
「セレナードに、カノンという町がありますよね。元々はモデラートの中の町でしたけど・・・」
「・・・は、い」
まだ呼吸が整わず、アルスは何とか相槌を打った。
「カノンは、セレナードとモデラートが統合した後も、セレナードに干渉されない姿勢を保っているらしいんです。」
「そ・・・そうなんですか」
「クラングさんとローチェさんがテヌートだったとしたら・・・カノンに行って調べてみる価値はあると思うんです・・・。
冷静になって考えることなんて、ここしばらくできる状態じゃなかったんですけど・・・」
「・・・あ、はい・・・」
イルの口調は、大分いつもの調子を取り戻していた。
「私がお二人の為に出来るせめてものことって、それぐらいだと思うんですよね」
イルは乱れていた服の首元を正しながらまたアルスに歩み寄った。
腰の帯もずれていたので巻き直している。
「ありがとうアルス・・・元気が出たのはアルスのおかげです・・・本当に、ありがとうございます」
「は・・・はい・・・よかったです・・・」
イルを見上げながら、アルスは涙だらけの目元を拭った。
慰めに来たのに自分ばかり泣いてしまって、とアルスは少し申し訳なく思った。
「バイエルをセレナードに送ってフレイに渡してきたら、カノンに寄ってみます。」
「で、でも、テヌートばっかりの地区に行って大丈夫ですか・・・?」
「大丈夫ですよ。私・・・半分はテヌートですから」
「・・・・・・!」
アルスは目を見開いて、口をぽかんと開けた。
「しばらく会えないかもしれないですけど・・・必ず調べて帰ってきますから。いい子で勉強してて下さい」
「え・・・あ・・・はい・・・」
頭の整理がつかなかったが、アルスはとりあえず口を閉じて、静かに頷いた。
―第五章に続く―

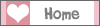
|